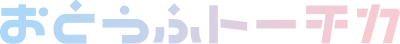まじめさは美徳ではあるけれど、行きすぎると難儀だなあ。こはねは自分の性質を棚上げしたことには気づかずそう思う。バレンタインから一週間ほど経ったが、冬弥は未だ残るチョコレートたちを必死に消費している。それは学校で義理だったりそうじゃなさそうだったり、とにかく差し出されたものをすべて受け取った結果だった。ひゅっと息をつめて砂糖のかたまりを飲み下す様子に、そんなに甘いものが苦手で去年まではどうしていたの、と訊くと雑談を交わすクラスメイトさえほとんどいなかったから経験していない、と返ってきたので驚いた。一目置かれていたといえば聞こえだけはいいが、実際は浮いていたのかもしれない。想像でしかない中学時代の彼の環境に心を痛めつつ、それはそれとして、とこはねはコーヒーカップを手にとるついでに隣に腰かけている冬弥をみる。
最後に残っていた箱入りのマカロンは、とてもじゃないが義理として同級生に渡す価格のものではない。けれどその価値についてこはねは特に指摘しない。だって訊かれていないから、と心中でいじわるな言い訳をする自分がいることは、知られてはならない。
「終わった……小豆沢、これで食べきったぞ」
最後にコップの水をひとくち飲み、カウンターに崩れ落ちながら呻くように冬弥が言った。今日まで毎度、静かに見守っていたメイコが微笑まじりにお疲れさま、と声をかけ淹れたてのコーヒーを静かに置く。
「次からはきちんと断ろうと思う」
「そうだね、がんばったね」
こはねが冬弥の静かな戦いに気がついたのは数日前、練習までぽっかりと時間があき何気なくメイコの店を訪れたときだった。いつもなら顔をあわせると微かに目元を緩めて挨拶をしてくる冬弥が、あわてるようにカウンターの上のものを隠そうとした。が、咄嗟に大きく動かした腕はそのなかのひとつを弾き飛ばした。うまい具合に自分の足元へ転がってきたそれを拾い上げ、こはねは首をかしげた。簡易的なプレゼント包装は、バレンタイン当日に冬弥が抱えていた紙袋のなかに見た覚えがある。クラスの誰それにもらったのだと言っていたが、どうしてそれが今ここにあるのだろう。ぱちりと目があった冬弥は、ちいさくため息をもらしながらつぶやいた。
「……どうしても沢山は食べられなくて、店の冷蔵庫に置かせてもらって少しずつ消費しているんだ」
「そ、そうなんだ……がんばってね」
そんな居残り給食みたいな、と出かかった言葉を飲み込んで、こはねは励ましの言葉をかけた。以降、なんとなく進捗が気になって隙間時間ができると冬弥の様子を見にくるようになり、今日に至る。
ようやく苦行――と言ってしまうのはあまりにも贈り主たちが不憫だが――を終えた冬弥は、突っ伏したままの体勢で首をひねってこはねに視線を向ける。しばらく無言のままみつめられ、こはねはなんとなく前髪を直した。ぼんやりとした様子に、無理して苦手なものを食べ続けたから具合がわるいのかと心配になる。
「青柳くん、大丈夫?」
「あまり大丈夫ではないな……」
「お口直ししたら? ほら、コーヒーもあるよ」
「口直し……」
いまいちしゃきっとしない受け答えが続いたが、ふと何かに気がついたみたいに冬弥がゆっくりと体を起こす。話そうとしたのか口をあけて息を吸いこみ、う、と顔をしかめた。
「鼻の奥まで甘ったるい」
「ちょっと外の空気でも吸ってきたら?」
見兼ねたメイコの言葉に従うようにして、二人は荷物を店内に残したまま扉の外へ出る。コートも置いてきたけれど、このセカイはいつだって安定した気候なので寒くはない。手持ち無沙汰にちらりと隣を見やると、冬弥がゆっくり息を吐きながらこはねに向き合った。何やらいつもよりわずかに張りつめた空気を感じてちいさく身じろぎしたこはねは、次の瞬間聞こえてきた言葉の意味を理解できなかった。
「小豆沢、吸わせてほしい」
「……え?」
およそ言われたことのない頼みに、完全に思考が止まる。
吸わせてほしい? なにを? ぱっと思い浮かぶのはストローで吸う、という行為だがカフェの外に飲み物は持ってきていない。ええと、と意味もなく両手を上げ下げして戸惑っていると、冬弥は確固たる意志をもった動きでこはねの肩をつかんだ。
「青柳くん? ちょっと待っ――」
こはねの制止が聞こえていないのか聞く気がないのか、冬弥の顔が上からのぞきこむように近づいてくる。逃れようもなく、半ば観念して強く目をつむったこはねが次に感じたのは、首筋に触れる髪の感触だった。え、と思ってうっすら目をあけてうかがうと、冬弥はこはねの肩あたりに額をつけてすん、と鼻を鳴らした。それから、実際は数秒程度だったがこはねにとっては長すぎるくらいの時間をかけて冬弥は二度ほど深呼吸をした。吐き出されたなまあたたかい息が首元から鎖骨のあたりにかかり、くすぐったさと恥ずかしさで背すじがこわばる。一体何をされているんだろう、と戸惑っている間に、冬弥はあっけないほどあっさりと体を離した。
「ありがとう、リセットできて落ち着いた」
「吸……吸った、の?」
わけがわからないまま、さっぱりした顔をして店に戻る冬弥の後ろ姿を呆然と眺める。キスでもされるのかと思って取り乱しかけたが、降りかかったのはその上を行く混乱だった。吸わせてほしいと言われたし、確かにそうされた。思わずたったいま冬弥が顔をうずめてきた肩口を自分でもかいでみて、とりあえず変なにおいはしてなさそうだとほっとする。それと同時に、人の髪の毛とはちがう細い繊維が袖についていることに気がついた。ゆびさきでつまんでよく見てみると、おそらく犬や猫の毛のようだ。今日は飼育委員の活動はなかったし、どこかで動物に触れた覚えもない。そういえば、冬弥の家は猫を飼っているときいたことがある。いまの接触時に付着したのだろう。
「あ」
そこまで考えて、こはねは急速に冬弥の行動原理を理解した。周りの猫飼いやネット上の猫好きがしばしば使っている独特の単語。猫を愛するがあまり暴走した人間の、変態的ともいえる愛情表現としてその行為は巷に存在している。
「ね、猫を吸うのと同じ感覚で私を……!?」
ふつうの感覚なら信じられないことだけど、時折そういう突飛なことを平然とやってのけるのが冬弥だ。それも、自分だけで納得して完結してしまうので始末がわるい。こんな変なこと、他の人にやらないように念押ししなくちゃ。こはねもまた若干ずれた方向の憤りを抱えながら、店に戻るべく駆けだした。