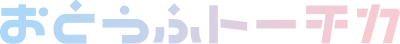がち、という硬質な響きの衝撃からすこし遅れて痺れるような痛みがくちびるの裏側に広がり、こはねは思わず口もとを両手で覆ってうつむいた。じわじわと熱くなってくる粘膜と滲む血の味を舌先に感じながら、視線だけ上に向けて相手を窺う。冬弥もまた、顔をかばうような姿勢で固まっていた。しばらく待ったが動き出しそうにないので、こはねは自分の肩に乗ったまま忘れ去られている気がする冬弥の左てのひらをそっとはがしてやってから声をかけた。
「だ、大丈夫……?」
「……すまない、失敗した」
「私こそごめんね、急に顔あげちゃって」
言いながら、たったいまのできごとが脳裏によみがえり、こはねは恥ずかしさと気まずさから一歩あとずさる。今日はもうまともに冬弥の顔を見られそうになく、ここは一旦解散してひとりになりたい。
「ええと、送ってくれてありがとう。おやすみなさい」
一方的にそれだけ伝え、手早く自宅の門を開けて玄関ポーチへ駆け込む。自分の陣地に帰ってきたことにいつも以上にほっと胸を撫で下ろし、未だ立ち尽くしたままの冬弥を物陰からこっそり見る。はっきりとは聞こえなかったが、何やらもごもごとつぶやいて片手で顔を覆っている。しばらく時が止まったようにそのままだったが、やがて深く息をついてからのそりと歩きはじめた。のろのろと遠ざかっていく背中を見送り、こはねもようやく扉を開ける。その間にもじわりじわりと滲んできていた血をもう一度舐めとり、大きく深呼吸した。
これだけ思いきりぶつかったのだから当然互いのくちびるは触れあったはずなのだけれど、まったく記憶に残っていない。果たしてこれはファーストキスにカウントしてもいいものなのか、ぼんやりした思考を抱えながらとぼとぼと自室へ向かった。
冬弥といわゆる恋人同士の関係になってからひと月ほど経つ。いつからだろうか、それぞれのスケジュールの都合で偶然二人きりになるのとは別に、他愛ない用事で誘ったり誘われたりを繰り返す日々がしばらく続いた。気がつけばチームの仲間としての信頼とは違う種類の感情を抱いていたけれど、もう一歩踏み込むための確信には届かず、ぬるま湯のような現状に甘えはじめたころ。めずらしくグループチャットではなく個人的に送られてきたメッセージを見て、こはねはへなへなとベッドに崩れ落ちた。
――小豆沢に明日告白しようと思うんだが、大丈夫だろうか
「告白、の予告……!?」
どう返すのが正解なのかわからないまま散々悩み、大丈夫です、と短く一言送った翌日。就職面接かはたまたお見合いでもしているのかと言いたくなるくらいにかしこまった態度の冬弥と向き合い、これってスタンダードなのかなあ、とこはねはすこしだけ遠い目をしながらその告白を受け入れた。
そんなふうに始まったから、というわけではないだろうけれど、キスひとつとってもすんなりとはいかない星の下らしい。
日も暮れたからと送ってもらった家の前で、またもやあらたまった様子の冬弥からキスをしてもいいだろうか、と訊かれた。付き合いはじめたといっても、その事実を杏たちに報告したほかはこれまでと大きく変わったことはなく、今日も早めに終わった練習のあと二人でショッピングモールを眺めて回った帰りだ。デートと呼ぶほどでもなく直前までまったく恋人らしい雰囲気はなかったので、心の準備もなにもなく無言で小刻みにうなずくのが精一杯だった。目をあわせるのも恥ずかしく、肩に手をかけられたのを合図にぎゅうと目をつむってしばらく。
「……?」
視界がふさがっているから長く感じるのだろうかと一瞬思ったが、覚悟した感触は一向におとずれない。考えてみれば二人の間には結構な身長差があるのに、こはねはうつむいた姿勢で待ってしまっている。
(きっと困らせちゃってるんだ、ちゃんとしなくちゃ……!)
そう思って勢いよく顔をあげた瞬間、ちょうどかがみ込んできたらしい冬弥との衝突事故が起きたのだった。
「青柳くん、大丈夫だったかなあ」
夕飯やお風呂をすませて寝支度にはいるころには、口内の傷は舌でさわるとほんのわずかにぷくりとした腫れを感じる程度におさまっていた。へたに咎めでもしなければこのまま治るだろう。鏡の前で声を出さずにあー、いー、と口を動かし、痛みがないことを確かめる。明日も放課後は練習の予定だ。キスに失敗して歌うのに支障が出るなんてことになったら、さすがに杏にも相談できない。
それにしても、とこはねはベッドへもぐりこみながら思う。出会ってからこれまで、冬弥への印象はまじめで落ち着いていて頼りになる、音楽活動の先輩だった。そのためつい色々と委ねてしまいがちだけれど、時折おどろくほど世間一般に疎い面もある。こと恋愛関係については、もしかしたらこはねと似たような経験値――要するにほぼゼロ――ではないかと思えてきた。そうだとしたら、受け身ではなく自分でもきちんと調べて勉強していかなければ。ひそやかだけれど強い決意を秘めながら、こはねは眠りに落ちた。
▽
気分が落ち込んでいるからか、いつもよりずしりと重く感じる玄関扉を開けて冬弥はそのまま一度へたり込んだ。
これまで、自分はそれなりにうまくやってきているタイプだと思っていた。親の期待にこそ応えられなかったが、言われたことをきちんとこなすという染みついた習慣のおかげか、学生の抱える苦労の大部分を占めるであろう勉強でつまづいたことはない。人付き合いだって、彰人のような広い人脈はなくとも誰かとトラブルを起こした経験もない。ただ最近なんとなく感じるのは、同世代と比べると見聞きしてきたものが少ないせいで対応力がないのかもしれない、ということだ。どれだけ本のなかの知識を漁ったって、それは冬弥の経験にはなりえない。
遠回りがすぎるくらい慎重に、自分の存在を彼女へ擦りこんでいった果てのぐだぐだの告白劇――彰人へ相談するつもりのメッセージを誤送信したときは完全に終わったと思った――からひと月ほどが過ぎたが彼女と過ごす時間は相変わらず、のどか、と言えばいいのだろうか。気持ちを伝える前に抱いていた不安や期待とは裏腹に、変わったことはないようだ。これでいいのかと心配になりいろいろと調べて目にしたのは、友人関係からなりゆきで付き合いはじめた場合の自然消滅率の高さについて力説した記事だった。そのたったひとりの主張を信じたわけではないが、冬弥に焦りをもたらしたのは確かだ。だから、流れとか雰囲気だとかを無視してまるでミッションでもこなすように切り出した。
キスをしたいと言い出したものの、目を伏せて待つこはねを前にして、どうすればいいのか考えていなかったことに気がついて冬弥は固まった。自分は目を閉じるのか開けたままなのか、息は止めているのか吸うのか吐くのか、何秒くらいが一般的なのか、そもそもキスってなんのための、何だ?
思考のどつぼにはまりながら、とにかく済ませてしまおうと冬弥が闇雲にかがみ込むのと、こはねが前触れなく顔をあげたのはほぼ同時だった。
風呂で温まって血行がよくなったのだろう、どくどくと主張してくる下くちびるの裏の傷を撫ぜながら冬弥は寝返りを打った。傷は思ったより深いようで、ろくにフォローも弁解もできず別れたこはねのことを考える。もしかしたら、ぶつけた自分の歯で彼女のことを傷つけてしまったかもしれない。自分より遥かに小柄でやわそうなこはねと付き合っていくなら、もっと慎重に、周到に準備をしていくべきなのだ。冬弥は決意を新たに、一度は枕元へ置いたスマートフォンへ手を伸ばした。
▽
「日曜日だから混んでるかと思ったけど、大きい部屋にしてもらえてよかったね」
「朝から雨だからな、人出が少ないんだろう」
言いながら、たたんだ傘の置き場所がみつけられず冬弥は室内をくるりと見回した。今日の集合場所はカラオケルームで、しばらく根を詰めて練習していたので息抜きにどうかと話が出た。息抜きといってもチームとしては選ばないような楽曲を遊び半分に入れて歌ってみるとあたらしい表現の可能性がみつかることもあり、気づいたらすっかり研究に熱中していた、なんて状況がお決まりだ。
「青柳くん、傘こっちにどうぞ」
声をかけられて振り向くと、こはねが部屋の隅を指していて、彼女の傘がすでに立てかけてある。それにならうように冬弥も傘を置き、ようやく荷物をおろしてソファに座った。
「杏ちゃんたちはあと三十分くらいで来られるって」
スマートフォンを見ながらこはねがためらいなく隣に腰をおろしたので、冬弥は思わず、え、とちいさく声を漏らす。
「どうかした?」
「いや、あっちに白石と座ったほうがいいんじゃないか」
テーブルを挟んだ向かいのソファに視線を向けてそう言うと、こはねはまるい目をぱちりと瞬いた。きょとん、と形容するのがぴったりだな、と思った矢先にみるみる頬を染めてうつむく。
「そ、そうだよね……二人きりだったから間違えちゃった。東雲くんがここに来るもんね」
か細い声とともに立ち上がろうとするのをこのまま見送るのはなんだか惜しい気がして、冬弥は咄嗟に手ぶりで制した。
「まだ来ないから」
ほんの十数秒前の発言と矛盾してしまった、ときまり悪く思ったが、こはねはすこしだけ迷いを見せてから元の位置に座り直してくれた。しばらく沈黙が続き、モニターから流れるリコメンド映像の賑やかしい音だけが響く。そういえば、二人だけで会うことはあっても、密室に二人きり、はこれまでなかったかもしれない。これはチャンスだ、と冬弥は無意識に唾を飲み下す。あの失態から一週間近く経ちその間もお互い変わりなく接してきたが、冬弥は研究と対策を重ねながら機会を窺っていた。
「小豆沢」
所在なさそうにスカートの裾をつまんでのばしていたこはねが、呼びかけに反応してちらりと視線を向ける。決意が鈍らないうちにと、冬弥は急ぎ気味に言葉を続けた。
「この間の挽回をさせてほしい」
「挽回? なにを?」
「ちゃんと練習してきたから、今度こそキスをしてもいいだろうか」
ふぇ、と空気の抜けるみたいな微かな音がこはねのくちびるの端から漏れる。見開いた目は、そのままこぼれ落ちるのではないかと思うほどだ。
「練習って、どうやって」
「イメージトレーニングだ」
「い、イメージ……」
「ああ。それで気づいたことだが、こうして座った状態のほうがやりやすい。今ならうまくできると思う」
「ええと、その……ううん……」
恥じらっているというよりは何かを言いよどむように、こはねは眉間に皺を寄せながら首を傾げる。平静を装いつつも、もしかして既に何か間違えただろうか、と冷や汗を滲ませたそのとき、こはねはまっすぐな眼差しを冬弥へ向けながら宣言した。
「わかった。しよう」
▽
あれやこれやとこまかい姿勢の注文に、こはねは素直に従った。まるでダンスのフォームを正しているような気持ちになり、そのあんまりなムードのなさにやはりこれは違うのでは、と思わないこともなかったけれど冬弥はそれを一旦無視して目の前の彼女をみつめる。言われるがままこころもち顎をあげた状態で、伏せたまつ毛がわずかに震えて白い頬に影を落としている。よし、と声には出さずうなずいて、両サイドから押さえるようにこはねの腕に手をかける。今度こそ失敗は許されない。緊張ぎみに引き結ばれたくちびるに顔を寄せながら、ふと、そういえばまだ手をつないだこともなかったな、とうっすら思った。
文字通りくちびるを軽く重ねただけのふに、とした感触に達成感を覚えて冬弥はこはねをつかんでいる手に力を込めた。それにしても、自分のそれと比べるとおどろくほどやわらかい。脳内で幾度も行ったシミュレーションでは一度だけすこし長めに触れるつもりだったが、予想外の感覚に臆してすぐに顔を離してしまった。こはねはというと、律儀に目をつむったまま動いていない。そこに甘んじて、もう一度だけそっと触れる。そのままついばんでしまいたい気持ちを抑えながら顔を離すと、わずかな間のあと、こはねがゆっくりとまぶたをあげた。
「……おわり?」
「え、」
不思議そうに訊かれ、意図がわからずぱちりと瞬きをする。自分が人のことを言えたものではないけれど、もっと照れるなどして甘やかな空気になるものなのでは、と戸惑っていると、こはねはどこか勇ましさをたたえた表情でぐい、とにじり寄ってきた。
「私もね、勉強してきたの。試してみてもいいかな」
疑問形の割には返事も待たず、がしりとシャツの胸元を――胸ぐらを――つかまれて、抵抗するひまもなく至近距離で視線が絡みあい、そしてさらりと流れる亜麻色の髪で視界が埋まる。同時に、ちゅ、とささやかなリップ音を鳴らしながらくちびるを吸われた。冬弥が落とした表面だけをなぞるかわいた口づけとは違い、内側の熱が伝わってきて背中にぞくりと震えが走る。離れたと思ったらまたすぐ食まれる、を何度か繰り返しているうちに互いの呼吸があってくるのがわかる。溶かされていく思考のなかで、タイミングがわからず溜まっていく唾液を飲み込もうとして反射的に閉じた冬弥のくちびるを、こはねは待ち構えていたようにぺろりと舐めた。
「あ、ずさわ、ちょ、ストップ……!」
このままでは飲み込まれる。防衛本能に似た何かがはたらき、冬弥は続けようとするこはねを引きはがした。激しく動いたわけでもないのに、どくどくと心臓は脈打っているし、じわりと汗もかいている。ストップをかけられたこはねもまた、頬を上気させてこちらを見ていた。それも、どこか満足気に。
「どうだった?」
「どうだった、って、一体なにを勉強してきたんだ小豆沢」
「キス」
「……一体なにで勉強してきたんだ」
冬弥の静かに問いただす声音に、こはねは急激に自信をなくしたかのように両手を胸の前で絡ませた。もじもじとこちらの様子を窺ってくるその様は、果たして先ほどの彼女と同一人物なのだろうかと疑問に思う。やがて、叱られ待ちの子どものように、ちいさな声で問いに答えた。
「……少女漫画」
「漫画!?」
思わず大きめの声が出てしまい、それを合図にこはねは一層萎縮して言い訳を並べた。
「だって、ドラマや映画はなんか恥ずかしくてじっくり観られないし、ネットで調べると見ちゃいけないものも出てくるからそれくらいしかなくて。私、間違っちゃったかな」
いまにも泣き出しそうな顔をされ、冬弥はかける言葉がすぐには出てこない。ルートは違えど、二人で同じことを考えていたのだ。これまでいまいち彼女の心情が見えてこなくて不安もあったが、少なくとも自然消滅するようなすれ違いはなさそうだ。それは喜ばしい。が。
「青柳くんもきっと調べたりしてくるはずだから、同じくらいがんばろうと思ったの」
「そう、だな……間違ってはない、のだろうな……」
なんだかひどく喉がかわいたな、とぼんやり考え、そういえばドリンクを取りに行くのも忘れていたことを思い出しながら冬弥はあいまいな言葉をつぶやく。
まずは、参考資料のすり合わせが必要だ。