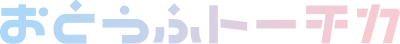何度目のスヌーズかわからないアラームを気力で止め、のばした腕をすぐに引っ込めてもういちど掛け布団にくるまる。窓を閉め切っていてもひんやりとした空気は防げず、自分の体温であたたまった居心地のいい寝床からはなかなか起き上がれない。結局、保険でかけていた机の上の置時計が電子音を響かせるまで杏は二度寝を満喫してしまった。
この三連休は土曜日を除いて練習日にあてている。最終日の今日は午前中から集まる予定で、待ち合わせの時刻まで余裕がない。開店時間までは父親の店のスペースを間借りするし、きっと合間に軽食くらい出してくれるだろう、と甘えることにして朝食を一旦あきらめ家を出る。気持ちよく晴れた冬の空気には特有の透明感があり、早足で歩くうちに寝ぼけた頭もはっきりしてきた。妙に晴れ着姿の人とすれ違うな、と思っていたけれど当然だ。杏たち高校生にとっては数ある祝日のひとつだけれど、成人の日だったと思い出す。店の客入りにはあまり影響のないタイプの催しとはいえ、今日の手伝いを断ってしまったことにすこしだけ申し訳なさを覚えながら扉を押し開ける。すでに他の三人は到着していて、ライブスペース横でおしゃべりをしている。そんないつもの光景に一秒でも早く加わりたくて、杏はドアベルの鳴る音を背に足取り軽く駆けだした。
▽
「彰人はスーツと袴どっちにするの?」
声出しを終え、遅い朝食がわりのキッシュプレートを胃におさめながら杏は向かいに座る彰人へ問いかけた。じきに開店時間のため、このあとはスタジオ練だ。同じく朝食を食べそこねたという彰人の分も父は気前よく用意してくれたので、こはねたちには先にスタジオに入って準備をしてもらうことにして別れていた。
「いきなりなんの話だよ」
サラダに混ぜ込まれた千切りのにんじんを器用によりわけながら、彰人は眉をつりあげる。カウンター奥には彼が尊敬している人物のひとりであるはずの杏の父も控えているのだけれど、最近はよそゆきの態度をあまり見せないなと思う。もっとも、父曰くはじめから素の尖った性格なんて透けてたぞ、ということなので今更意味もないらしい。
「成人式の話。今日あちこちで振袖の人見たからさ、みんなはどうするのかなあって」
「気が早すぎるだろ。うちはまず姉貴だし、そもそも男より女のほうが親も気合入れるだろうし。オレはどうだか」
「あ、そっか。年子ってそういうの忙しそうだね。こはねはお父さんの様子からしてきっと全力で支度されるんだろうなあ。冬弥の家もなんとなくだけど凝りそうだし、見るのが楽しみかも」
まだまだ先の光景をぼんやりと思い浮かべながらそう言うと、彰人はなぜか呆れたような表情をみせた。
「というか、成人になってもこの調子でつるんでるつもりなのかよ」
それは、杏がすこしも疑わず信じている未来に水を差すひとことだった。もちろんこの先なにがあるかは誰にもわからないけれど、夢を同じくする限りは何年経っても一緒にいるつもりで活動しているのだ。こはねたちとはその感度が同じだと思えるが、彰人は時折、杏からすると冷淡に感じる物言いをする。目標へのがむしゃらさは人一倍のくせに、ひとりだけ大人ぶっているみたいで、おもしろくない。
「たかが数年であの夜を超えられると思ってるほうがおかしいですけど?」
「いや、チームの存続の話じゃねえよ」
反射的に喧嘩腰でふっかけた杏の売り言葉には乗らず、彰人は淡々と続ける。
「お互いプライベートもあるだろうし、成人式の日まで四人で会うのかっつー話」
「え、会わない可能性ある?」
「だからそれぞれの付き合いがあるだろ。中学とか、場合によっては大学の同期とか、あとは家族や恋人とか、優先すべき関係が」
彰人から何気なく発された恋人、の単語に動揺して、杏は飲みかけていた水をあやうく吹き出すところだった。揺れた手元のせいで、がちりと前歯にガラスの縁がぶつかる。その一瞬の流れをごまかすように慎重にコップを机に戻し、結露で濡れた指先を紙ナプキンに押しつけた。何か言われるより早く、と焦って口を開く。
「そりゃあそうかもしれないけど……私はその日だって、まずみんなに会いたいな。彰人はちがうの?」
「……どうだろうな」
それは問いへの返答というにはちいさく、ひとりごとのようだった。いつの間にか食事を終えて頬杖をついている彰人の視線は、どことも言えない半端な高さへ向けられている。目の前にいるくせに杏とは見えているものがちがうみたいで、胸の奥がざわりとした。彰人はしばらくそのまま黙っていたが、ふいにだらりと脱力していつもの調子に戻って言う。
「まあでも、お前がこのまま変わってなければオレもそこにいると思うわ。残念ながら」
「え、どういうこと?」
自分でもわかる程度にまのぬけた声が出たが、彰人はそれには答えず軽く肩をすくめて席を立つ。ごちそうさまです、と店の奥へ声をかけると特に杏を待ってくれる素振りもなく店を出ていくので、あわてて追いかけた。扉を開ければ暖房のきいた室内から急に外気に触れ、ぶるりと体が震える。外に出ると、数歩先で足を止めてこちらを振り返っている彰人の姿が見えて拍子抜けする。最初からあわせてくれたらいいのに、と思いながら歩幅を大きくして一気に追いついた。
「私、そう簡単には変わる予定ないからね」
「はは、めんど」
みんなで集まる成人式、という杏のビジョンに否定的な彰人への宣戦布告のつもりでそう言ったのに、返ってきたのは妙にやわらかな声だった。思わず顔をあげると、彰人は笑みを浮かべていた。それは呆れたようなあきらめたような、ともすれば相手を甘やかすような不思議なニュアンスだったが、杏はやはりその意味がわからずあいまいに首をひねっただけだった。