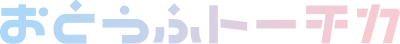昼休み、彰人がいつもどおり冬弥の教室へ向かうと、めずらしく自席でクラスメイトと話している冬弥が目に入った。ちらりと目が合い軽く手ぶりで招かれたので遠慮せずそばまで寄る。会話相手には彰人も見覚えがあった。授業中――よほど熱心でなければ手持ち無沙汰になりがちな化学の実験中――に、ちょっとした雑談から冬弥たちの活動を知り、自分もバンドを組んでいるからと興味を持ったクラスメイトがいたのでライブに誘った、という話を聞いたのがすこし前。彼が実際に見にきて出演後に声をかけてきたのが昨日のことだ。すごいな、かっこよかったぜ、と適当なことを言ってすぐ帰っていったよな、と思い出していると、やや興奮ぎみに話す声が聞こえてきた。
「あの白石じゃないほうの女子、うちの生徒にいたっけ」
「いや、小豆沢は宮女に通っている」
「まじか、お嬢さまじゃん。え、同い年?」
「そうだ」
「そっかあ……いいな、かわいかったなあ」
なるほどな、とクラスメイトの意図を察して彰人はその言葉を受けた冬弥の様子を窺う。こういう会話は慣れていないだろうしてっきり戸惑っているかと思ったが、冬弥は真顔で深くうなずいた。
「ああ、かわいいだろう。最近ステージ上では堂々とできるようになったが、普段は表情もくるくる変わるしもっとかわいいぞ」
予想外の返しに、喉からぐぎょ、と空気のつぶれる変な音が出て彰人は咳き込むふりをしてごまかす。べつに避けているつもりはないが、冬弥とこの手合いの話をする機会はほとんどないのでこはねに対してそんな風に思っているのは初耳である。その平らかなトーンからとくべつな感情が乗っているのかは判断しかねるものの、よくもまあ顔色ひとつ変えずに言えるな、と半ば尊敬する。相手も、呆気にとられた顔で口が半開きだ。
「……付き合ってるとかじゃないんだよな?」
「誰が?」
「おまえとその子」
「そういう話はしたことがないな」
「じゃあ紹介してって言ったらいける?」
しぶとく話を続ける男子のガッツに感心しつつ、再び冬弥の反応を見る。すると今度は困ったように眉根を寄せて考えはじめた。そこには拒否感あるのか、じゃあ好きじゃねえか、とむずがゆく思う。けれど、申し訳なさそうに発した冬弥の言葉はまたしても彰人を咳き込ませた。
「……すまないが、俺たちチームからは小豆沢はもちろん、誰も貸せないな。ボーカルを探しているのなら協力はしてやりたいが」
「冬弥、おま、おまえさあ」
「あ、いいです。青柳、おまえって結構曲者だな……」
思わず口を挟んだ彰人を遮るようにそう言い、クラスメイトは苦笑を残し席を離れた。二人になってはじめて、冬弥は採点でも待つような顔をしてそばに立つ彰人を見上げる。
「気を悪くしただろうか、話が合うと思ったんだが」
「どの部分でそう思えたんだ……?」
今のところそういうつもりではなさそうだが、この調子で無意識に囲い込まれていくであろうこはねにどこか同情を覚えながら、彰人は天然っておそろしいよな、と呆れぎみにつぶやいた。