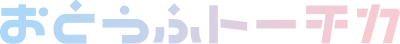もう昼前だというのに、昨晩の雨模様から続く曇り空のせいで気温がまったくあがらない。耳たぶにふれるピアスキャッチのわずかな接触面のつめたさにうへえ、と声を漏らしながら彰人は支度を終えて家を出た。濡れた地面が冷やされて、独特のにおいが鼻につく。今日はこれからスタジオ練の予定だ。現地集合のためひとりで向かう途中、人通りのなかに冬弥の見慣れた後ろ姿をみとめ、声をかける。
「おはよ」
返事がないので不審に思ってよくみると、どうやら音楽を聴いているらしく気がついていない。ゆびさきの暖をとっているポケットから手を出す気にもなれず、肩をぶつけて主張する。ようやくこちらへ視線を向けた冬弥は、耳からイヤホンを外してコートのポケットへ放り込んだ。
「彰人か、おはよう」
「それ、ちゃんと外音取り込みしてるか?」
「大丈夫だ、ただぼんやり歩いていただけだから」
「それはそれで危ないんだけどな」
騒がしいほうが気が紛れるとは冬弥の弁だが、聞くに堪えない音も含めてあふれているのがこの街である。よかれと思って勧めたノイズキャンセリング付きのイヤホンのなかから迷わずいちばん高いグレードのものを買ったのには驚いたが、無事活用しているようで何よりだと思う。
「それにしても寒いな、ヘッドホンにすればよかった。耳がちぎれそうだ」
「今日は気温二桁いかないらしいぜ、こういう寒い日にサッカー部の助っ人なんかで長時間走り回るとさ、口の中が鉄の味するよな」
「鉄の……? 経験がないな」
彰人からしたら冬のよくある話だったが、冬弥には覚えがないようで通じない。本当に運動しないんだな、とあらためて感じていると、冬弥も同じようなことを口にした。
「白石もそうだが、授業以外で積極的に運動する気になるのはすごいな」
「そうかあ? 勉強よりよっぽど楽だしやって悪いこともねえし、難しい話じゃねえよ。お前だって家で筋トレくらいはやってるんだろ?」
出会ってじきのころ、より良い歌を歌うためにといくつかのトレーニングを当時の受け売りで教えた記憶が彰人にはある。歌うのに筋力も重要であることは事実だし、まじめな冬弥はそこを切り口にいろいろ調べてアップデートしているだろう。
「あれは続けている。が、俺にはそれくらいで充分だな」
「ふーん、お前はオレより背もあるしもったいない気もするけど、まあ人それぞれだからな……うわ、あぶね」
区切りよくスタジオの前に着いたので階段を二段飛びにあがろうとして、彰人は足元の違和感に一度踏みとどまる。階段下のすこしだけ窪んだアスファルトの表面に、広くうっすらと氷が張っている。踏み壊そうにも、こまかいおうとつに張られた氷にはつま先も踵も届かない。あとで中のスタッフに伝えようと考えながら、彰人はひょいと飛び越えた。
「そこ凍ってるから気をつけろよ」
「ああ」
わかっていればなんてことはなく、冬弥もまたいでエントランスの低い階段に足を乗せる。ちょうどそのとき、背後からよく通るあかるい声がかかった。
「おはよ! みんな同じタイミングだったみたいだね」
振り返ると、杏とこはねが並んで向かってきていた。軽く手をあげて応じ、念のためにと注意を促す。
「階段下のとこ、凍ってるからコケねえようにな」
「え? なに?」
聞き取れなかったのか、杏が駆け足になりこはねも置いてかれまいと足を早めたので彰人は大きめに声を出す。
「だから階段のところに氷が……」
言い終わるより早く、杏は凍結した地面に勢いよく靴底をすべらせた。ほとんど同時にこはねも続き、二人仲良くずるりと体勢を崩す。
「わあっ」
「ひゃあ……!」
そろって前のめりに倒れてくるので、彰人はあわてて階段を降りた。
「バカかお前ら」
毒づきながら、咄嗟に腕をのばして杏の体を引っかけるように支える。ぼすん、と飛び込んできた重みを受け止め、隣のこはねを助けなかったのは冬弥が動くのを視界の端で確認したからであって、見捨てたり優先順位をつけたりしたわけではない、と心の中で言い訳をした。
「うわ、びっくりした」
「それはこっちの台詞だ、人の話はちゃんと聞け」
「言うのが遅いんだってば」
遠慮なくがしりとつかまって転倒を防ぐことに成功した杏は、ふるふると頭を振ってから体を離して彰人を見上げてくる。そのてらいのない瞳に、続けようとしていた反論を思わず飲み込んでしまう。常時まっすぐな性質である彼女が濁りそうになるのは、決まってこはね絡みのときだと知っている。別にそこに思うことはないはずなのだけれど、なんとなく面白くない気持ちが湧き上がりでこぴんのひとつでもしてやろうか、と指を丸めかけたとき、すぐそばから悲痛な声が聞こえてきた。
「ご、ごめんね青柳くん、大丈夫!? 頭とか打ってない? それに、お尻濡れちゃったんじゃ……」
なにごとかと視線を落とせば、アスファルトに座り込んだ――というか、ほとんど寝転んだ――冬弥の傍で、こはねがあわあわと取り乱していた。どうやら、突っ込んできたこはねを支えきれずひっくり返ったらしい。確かに彰人と比べれば反射神経が良いわけではないにしても、これはすこし、いや、かなり恥ずかしい状況である。
「……問題ない。小豆沢こそ、怪我はしてないか」
「私は青柳くんのおかげで大丈夫だけど……」
「うわー、二人とも平気!? タオル使う?」
「杏、こっち来い」
限りなく抑えられた声音から、冬弥の気まずさを察知した彰人はそそくさと杏の手を引いてスタジオのガラス扉を押し開けた。とりあえず、彼のフォローはこはねに託そう。
「冬弥はそのへんでジャージでも買って着替えさせるから、お前は先に受け付け済ませてこいよ」
「あっ、なるほど。いってくる」
素直に納得してぱたぱたと奥のカウンターへ向かう杏を見送り、ガラスの向こうに視線を戻す。こはねが差し出した手を断った冬弥がのそりと立ち上がるのが見えた。
フィジカルを鍛えたいのだが、という冬弥からの相談のメッセージが届いたのは、その晩の日付が変わるころだった。