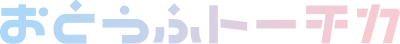「ほんっと、楽しかったなあこはねとのデート。また行こうね!」
「うん、今度は杏ちゃんが好きな場所に行きたいな」
ここ数日で何度目かも数えきれない杏の言葉に、こはねも繰り返し答える。楽しんでくれたのは事実だろうし、あの日すこしだけ翳ったこはねの心情に気がついてくれた彼女なりのフォローが続いているのか、と考えると何回でも喜んでしまう。
「いつまで引っ張るんだよその話、ほら始めっぞ」
やや呆れた態度の彰人が口を挟み、それを合図に気持ちを切り替えて練習に臨む。文化祭も定期試験も終えたこの時期は、日が落ちるのが一層早い。そのせいで窓の外の暗さにも慣れ、いつもより遅い時間になったことに気がつかないことも増えてきた。
とくにそう決めた覚えもないけれど、帰りが十九時を回るときは冬弥が送ってくれることが当たり前になっている。今日もまたにぎわう大通りを並んで歩きながら他愛ない雑談をしていたが、どことなく反応が鈍い気がしてこはねは一度口を閉じた。沈黙がしばらく続いても、冬弥がそれを気にしている様子はない。何かあったの、と問いかけようとした瞬間、わずかに先を歩いていた冬弥が振り向きざまに言葉を発した。
「小豆沢は、俺ともデートをするべきだと思う」
「……えっと、ええ……?」
一体どこにその確信を得たのか、これしかないと言いたげに力のこもったまなじりに、こはねは戸惑いを隠せなかった。
▽
誰かに宣言したわけでもないが、こはねはいちおう冬弥とは付き合っているつもりである。ひと月ほど前、今日のように二人で話しながらの帰り道でテスト期間を挟むので次に会うまですこし間があくね、と何気なく話題にしていた。その別れ際、不意に手を引かれたと思ったら、冬弥はまっすぐすぎるくらいの眼差しでこちらを見てとんでもないことを言った。
キスをしてもいいだろうか、と。
当然だけれど告白してもされてもいないのに、突然そんなことを言うのでこはねの思考は完全に停止した。ただ、じわりと思ったのは自分がここしばらく抱えていた感情――もしかして、お互いに同じ気持ちなのではないかという淡い期待――が間違っていなかったということだった。どう答えればいいのか迷いながらかろうじて微かにうなずくと、ほとんど掠めるだけの早押しみたいなキスを落とされた。咄嗟につむった目をおそるおそるあけると、冬弥はそれじゃあ、とずいぶんあっさり言って来た道を戻っていったが、こはねはしばらく動けなかった。
どこか現実味のないまま帰宅し、それから二週間弱が過ぎて久しぶりに四人そろって顔をあわせたとき、こはねの緊張をよそに冬弥はそれ以前とまったく変わらない。あれはもしかして夢かなにかだったのだろうか、と不安に思ったが、へたにつつくのも怖くてそのままにしていた。
ひょっとしたら、たとえばペットを撫でるくらいの感覚でちょっとキスをしてみたかっただけなのかもしれない。とまで考えていたところに今度はいきなりデートなどと言い出した。こはねは慎重に冬弥の意図を探る。
「青柳くんも、フェニラン行きたいの?」
「いや、こだわらないができればそこ以外がいい。白石と行ったことのない場所が望ましい」
いつもなら通り過ぎる駅前の広場で、冬弥はめざとく空いたベンチをみつけて場所を確保した。この話を中途半端に終わらせるつもりがないと知り、こはねも隣に座った。目の前にはあふれるほどの人波が行き交い、この街がこれからよりにぎわっていくことを予感させる。誰も二人の会話に意識を向けないし、仮に顔見知りが通ったとしても簡単には声は聞こえないだろう。そう考えるとすこしだけ気が大きくなり、思い切って問いかけた。
「……もしかして青柳くん、やきもちやいてる?」
「あれだけ言われるとさすがにそうだな」
こころもち眉根を寄せてそう言う冬弥に、こはねはようやくこの一か月の答えを得た気がした。ペット扱いで戯れられたわけではなさそうだ。
「いいよ、デートしよう。どこに行こうか」
「どういうのが定番なんだ?」
「私にそれを訊かれても……ど、動物園とか?」
言いながらこれでは休日のお父さんみたいだ、と思う。テーマパークがだめとなると思い浮かぶ典型的な娯楽施設が動物園だなんて、小学生のころから成長していないようで恥ずかしさを覚える。映画館あたりにしておけばよかった、と後悔するこはねをよそに、冬弥は神妙な面持ちでうなずいた。
「小豆沢は動物が好きなんだな。それでいこう」
▽
「白石はマルメタピオカガエルに興奮する小豆沢を見たことはあるか?」
「えごめん、いきなり意味が分からないしなんか気持ちわるいんだけど……」
週明け、得意げな顔をした冬弥がそんなようなことをいくつも言うのでこはねは杏に一から説明をするはめになった挙句、のろけじゃん! と憤慨されることになった。