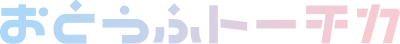「二人とも、人の手づくりした食べ物って平気?」
それは次のライブに向けた相談ごとが一通り済み、とりとめのない雑談がかわされる中で投げかけられた問いだった。彰人は今まさに頬張ろうとしていたパンケーキのひとかけをフォークごと指揮棒よろしくこはねの鼻先へ向け、素っ気なく答える。
「平気じゃなかったら何食って生きてくんだよ」
「お店のじゃなくて、クラスメイトとかの手づくりの話だよ……」
「うわ、しなくていい意地悪してる」
「ヤマが外れて補習になったから気が立ってるんだろう」
こはねが表情を曇らせると、たちまち二方向から擁護が飛んでくる。べつに険悪なわけではなく、日頃からもっと堂々とすればいいのに、と思っているための強めの物言いで、それは彼女以外の二人には伝わっているはずだ。
「他人が握ったおにぎりが食えるかってやつだろ? ある程度知ってる奴なら何とも思わねえけど」
あらためて向き合いながら、質問の意図を汲んで返す。彰人が軽くあごを上げて隣の相棒を見やると、冬弥は神妙な顔をしていた。
「俺はそういう機会もあまりなかったしよく分からないが……積極的には口にしないかもしれない」
「お前はそうかもな、慣れてないというか」
最近はそうでもないことを彰人も知っているが、交友関係が広いとは言えない生活を送ってきた冬弥は、対人の経験値が軒並み低い。
「確かに、慣れてはいないな」
得手不得手ではなく、と納得してうなずく様子を、こはねもまた真剣な面持ちでみていた。
▽
何事にも慎重でまじめに取り組むことは、褒められこそすれ非難されるいわれはない性質だ。けれど、これはすこし面倒だ、と彰人は手の中のささやかな包みを持て余して思う。二月になってからは毎日のようにどこかで目につき、聞こえてくるバレンタインという行事だが、わざわざ記憶にとどめるほどでもなかったあの会話は年が明けてすぐの頃だった。さすがにあの時期にそこまで察するのは無理だろ、と恨めしく思いながら彰人は隣を歩く冬弥をこっそり窺った。
店の常連にと杏が配ってきた――渡すとか贈るとかでなく、あれは完全に配布だったと彰人は思う――チョコは冬弥も受け取っていたが、こはねが彰人へ声をかけてきたのは、冬弥が先に店の外へ出た直後だった。いつもお世話になっています、とかしこまった言葉と共に渡された包みは、きれいにリボンが結ばれているがちいさなもので、これもまた義理だと一目でわかる。
「おう、どうも」
店の奥、カウンター側から杏がいたずらっぽい瞳で見てきているのを感じ、思ったより不機嫌そうな声が出てしまい内心で舌打ちをした。当然のように二人分の包みを待ったがしばらく経ってもこはねが追加を取り出す気配がなく、二人の間に妙な間ができる。
「あ、渡せってこと?」
「え? 東雲くんにあげる分だけど……青柳くんは手づくり嫌かなって思って。気を遣わせちゃいそうで」
小首を傾げてそう言い切る彼女に悪気はないのだろうが、どうしてそうなるんだよ、といらつきながら扉を開ける。ほんの数十秒のやりとりだったが、外で待つ冬弥は寒さに肩を強張らせながら立っていた。
「悪ぃ、帰ろうぜ」
右手を包みごとポケットへ突っ込み、まだ人通りの多い夜の街へ足を踏み出す。たったいま店内で起こったことについて気取られないかとひやひやしたが、冬弥はとくに言葉もなく並んで歩きはじめる。その横顔はいつもと変わらない澄ましたものだ。体の動きにあわせてポケットの中の指先にくしゃりとした感触がふれるたびに、気まずい思いが蓄積されていく。こそこそと様子を窺いながらどうしたものかと彰人が眉根を寄せるのと、冬弥が前を向いたまま口を開いたのはほぼ同時だった。
「……さっき、小豆沢と何を話してたんだ?」
その声がいつもより硬質なものに聞こえたのは寒さのせいか別の原因か、何にせよ冬弥から切り出してくれたことはありがたかった。訊かれたからと答えるほうが、自分で言い出すよりよほど楽だ。
「これだよ、バレンタイン」
手持ち無沙汰から無意識につつき回していたらしく、もらった時より形のくずれたそれを冬弥の眼前に掲げる。冬弥はまばたきもせず数秒だけ動きを止め、店を出てからはじめて彰人の顔を見た。二年前、いや、ほんの半年前と比べてもずいぶんやわらかくなったと感じていた冬弥の表情が、凪いだように消えている。
「誤解がないように言っておくけど、絶対的に義理だからな?」
こはねが通うのは女子校であり、バレンタインにはそれぞれが手づくりしたチョコなどを交換しあって食べるのが慣習だと聞いていた。要するに、そのお祭りごとの余りに過ぎない。そんな些細なものを渡すだけなのに、相手が受け入れられるか下調べをする彼女のまじめさは筋金入りだ。それがしばしばずれた結果になるところも含めて、この相棒と似ていると彰人は思っている。
「それでも、誰にでも渡してるわけじゃないだろう」
「誰にでもだよ。お前に渡さなかったのはあいつの気遣いだ」
「気遣い?」
穏やかであまり抑揚のない話し方が常の冬弥だが、めずらしく感情を滲ませた声が聞こえて彰人はわずかに目を瞠る。たった一言の中に、納得できない、という気持ちがこもっているようだった。初めて会ったときは考えもしなかった展開だが、こはねは彼にとってずいぶんとこだわりのある存在になったらしい。
「覚えてるか分かんねえけど……ちょっと前に手づくりを食えるかって会話しただろ。お前の性格上、苦手でも断らないと思ったから今回は避けたんだろうよ」
実際は彼女から明確に、冬弥へ渡さない選択をしたことを聞いていたがさすがにそこは隠して説明する。執着を持った相手のことは自分がいちばん把握していたいし、していると思いたい。という機微には彰人も覚えがある。
「……あれか……」
記憶をたどっていたらしい冬弥が遠い目をしてぼやき、再び黙り込む。あんなわずかな会話で命運が決まるなんてかわいそうだと、彰人は思わず声をかけた。
「いるか? これ」
「いや、いい。それは彰人がもらったものだ」
提案してみたものの、そりゃあ断るよな、と納得して差し出しかけた手を引っ込める。とはいえ、こはねには悪いがこのあとでこれを自分が食べる気にもなれなかった。きっと家に着いたら机の隅にでも放り出して、忘れたふりをして時を待ち捨てるだろう。なんとも言えない居心地のわるさに、彰人は寒空を仰ぐ。そのあとは、また沈黙が降りた。
「小豆沢は、来年も訊いてくれるだろうか」
そろそろで互いの帰路がわかれるころ、ぽつりと冬弥がつぶやいた。ああそうだな、と安請け合いしかけて、ふと違和感に気づく。
「いや、来年も同じ関係のつもりなのか?」
彰人にとっては自然な疑問だったが、それを受けた冬弥はいちど言葉の意味を咀嚼するように眼を眇め、それからどこか痛みでもするのかという重々しさでうなずいた。
「確かに、来年も彼女がフリーとは限らないか。恋人がいたらさすがに義理でも厳しいだろうな……」
「いや、だからお前が進展させろよ」
どうしてか第三者のようなことを言う冬弥にすかさず突っ込んだが、当人は不思議そうに首を傾げる。その空気感は先ほどこはねが醸し出していたものとやはり似ていた。
「俺が? なにを?」
「お、おまえ……まじかよ……」
ここまで散々、彼女への並々ならぬ思いを漏らしておいて自覚がない。彰人は呆れを通り越して恐ろしさを覚えたが、そういえば、この相棒は対人関係の経験値が年齢に見合わない低さだったと思い至る。人間的な相性はよさそうだが、恋愛面では苦労しそうな冬弥とこはねを脳裏に並べて彰人はため息をつく。吐いた息が白いもやとなり消えていくまで、別々の意味で途方に暮れた二人は立ち尽くしていた。