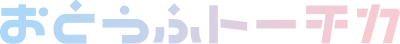繰り返し世話になっているライブハウスから季節イベントをやるからと声をかけられ、断る理由もなく二つ返事で参加を決めたのがひと月ほど前。日が近づいて送られてきた詳細メールに、四人とも一瞬目を瞠った。ハロウィンスペシャルホラーナイト、と銘打たれたタイトルの下には、演者も客も仮装してくる旨書かれていた。
「仮装って、どれくらいの規模を期待されてるのかなあ……」
「そんなに構えることないよ、ライブのおまけ要素でしょ」
買ってはみたものの、果たしてこれでいいのかというチープなつくりの猫耳カチューシャを不安そうにつまみあげてこはねがため息を漏らす。向かい合う杏は、派手な黄色のビニール袋に入れたままだった品々を取り出して控室のテーブルへ並べている。
「こういうバラエティ色のあるイベントは気が進まねえな」
「あの時は彰人もほとんど話聞かないで受けたじゃん」
お決まりの喧嘩が始まりそうな気配に、冬弥は相棒を止めに入る。
「そんなことより、今日は着替えもあるから早く支度を始めないと」
控室とは名ばかりの、ほとんど荷物だけでいっぱいの小部屋を出て男二人はトイレでもそもそと衣裳を身につける。彰人は狼男、冬弥は吸血鬼の、ディスカウントストアで買ったと一目で分かるような安易な仮装だが、ライブハウスの薄暗い照明の下ならこれで充分なのかもしれない。しばらく廊下でグループチャットの連絡を待ち、着替え完了の報告と共に部屋へ戻った。
「うわ、なんか二人とも黒いな。杏はそれなに、ダンゴムシか?」
「化け猫ですけど?」
「小豆沢は……死神?」
「魔女だよ、出るときはこの帽子かぶるからそれっぽく見えると思うけど……杏ちゃんも耳つけるもんね」
「まあね~。ほら、それより男子たちのメイクしよ」
ライブの中の遊び要素とはいえ、あまりにお粗末でも雰囲気を壊してしまう。歌えば当然、見る側の意識は顔へ向くため服装が間に合わせでもメイクがしっかりしていればいいだろう。というのが四人の結論だった。杏とこはねは既に、いつもよりくっきりとした印象にできあがっていた。椅子へ腰かけた冬弥をのぞきこむように身をかがめたこはねの口元が滲むように赤く、冬弥は見たまま感想を述べる。
「絵の具みたいに色がつくんだな」
「うん、ティントだから。いつもはグロスだし色も違うから、自分でもちょっと慣れないかな」
「なるほど」
出された単語がどれも理解できず、とりあえずうなずいて流す。こはねは特に気にした様子もなく、ペンのような道具のパッケージを開けている。手の甲に何度か試し書き、ぐっと拳を握った。
「よし。青柳くん、前髪あげてて。あと目もつむって」
言われるがままに右手で額を押さえてまぶたを閉じ、じっと息をひそめる。メイクをするのだから当たり前だけれど、じっくり見られていると思うと落ち着かない気持ちになる。日ごろ気にしたことはなかったが、人と違う特徴などはあっただろうか、と冬弥は自分の顔を思い出そうとしてみたがうまく浮かべることができない。じきに、目の際をぺとりとした筆のような感触がなぞっていくのを感じた。まずは左目、次は右。一度、あっ、と声がしてウェットティッシュ――おそらく違うけれど、冬弥の知識ではそう形容するしかなかった――でごしごしとこすられたりしながら終わるのを待った。
「青柳くん、一旦目あけて」
視界を奪われた状態というのはもどかしく長く感じるもので、冬弥は勢いよくぱちりと目をひらいた。だから完全に油断していて、向き合ったこはねの顔の近さに虚をつかれひゅっと息をのむ。
「あれ、やっぱり右がちょっと下がっちゃった……けど下のラインでごまかせるかな。このままいこう。青柳くん、今からは目つむらないように気をつけてね」
冬弥のひそかな動揺は幸いにも伝わらず、真剣な面持ちでこはねは次の工程に取りかかる。普段ではありえないくらいの距離感だけれど、職人のような表情になったこはねはいつもの照れも遠慮もどこかへ置き去りにしたらしい。黙々と筆を進める彼女が満足するまで、それから体感で五分以上かかった。
「これでいいかな?」
気づけば冬弥を固定するようにつかんでいた肩から手を放し、こはねは一歩ひいて自分の仕事を確認する。
「わあ、もともと切れ長だけどこうすると目力がすごい……青柳くん、きれいな顔してるね」
「……ありがとう」
妙なタイミングではあるが褒められたのだから、と律儀に礼を言った冬弥だが、心中はそれどころではなかった。作業中の彼女と視線が合うことこそなかったが、半ば強制的にこはねをみつめる数分間だった。それは、共に活動するようになってからここまで、無意識下に避けてきたことだった。パフォーマンス中やその練習をしている時は仲間もしくは後輩として見守る気持ちが強く観察していたが、それ以外の時において、冬弥はこはねのことをなんとなく薄目で見ていた。正面からはっきり見たら、くらってしまうことを察知していたからだ。
「よし、アイライン終わったから次は――」
「待ってくれ、まだあるのか」
「もちろん」
「その、教えてくれたら自分でやりたいのだが」
「そう? 時間大丈夫かなあ……杏ちゃん!」
段取りを相談するべく相棒のもとへ駆け寄るこはねを視界の端で見送って、冬弥は深く息をつき力を抜いた。
ぱちぱちとまばたきを繰り返すまるく大きな目、控えめなようでいて強い意思をたたえる引き結んだ唇、全体的に淡い印象を持つ瞳やそれをふちどる睫毛の色彩。客観的に見たら大抵の人間ははじめに浮かぶだろうひとことを、これまでずっと考えないようにしていた。
小豆沢こはねは、普通に可愛い。ごくシンプルに、女の子として。
一度意識してしまったら、何かが変わってしまう。知らない感情から逃げようとしていた冬弥の抵抗は、あえなく終わりを迎えたのだった。