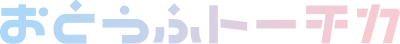こんな偶然が起こるなんて、やっぱり東京はすごい。俺はレジを打つことも忘れて目の前に立つ人物をみつめていた。
記憶にあるより大人びているけれど、繰り返し見ていた動画は古いものだし、何より特徴的なツートンカラーの髪が人違いではありえないと主張してくる。
「あの、何か」
「あっ!? すんません、お待たせしました!」
不思議そうにこちらをうかがう彼の視線から逃げるように、慌てて商品のスキャンを再開する。最後にカウンターに置かれたポイントカードを読み込むと、不可抗力で会員名が目に飛び込んできた。
(青柳……こはね?)
絶対にないとは言い切れないが、男性にはそぐわない印象だ。ひょっとして、ペットの名前だろうか。本来は客本人の記名をするべき欄だけれど、ペット用品店という意識がはたらくのか、ペットの名前を書いてしまう飼い主は珍しくない。セールのおしらせを発送するときなんて、ココアだとかおもちだとか、そういった宛名が束になっている。
「ありがとうございましたー」
なんとかその場を乗り切り、彼の背中を見送る。ふう、と息を吐き、次の客の対応に集中していく。駐車券は断っていたし、おそらく近所に住んでいるのだろう。購入したのは猫用のフードだったから、ここでバイトを続けていればいずれまた会うかもしれない、そう思うと落ち着かない気持ちになってしまう。
中学生のころ、SNSでたまたま見つけて引き込まれたローカルなゲーム大会の切り抜き動画。そのなかで目にも止まらぬぷよ捌きをしていた人物こそ、たった今買い物をしていった彼、青柳さんだ。その技術はトップレベル――というわけではなかったけれど、地域の大会で無双できるくらいには十二分にうまくて、さらに外見も目を引いた。どこか異質な姿勢のよさだとか、迷いのない視線とか。名も知らないその高校生に、俺は無性に憧れを抱いたのだ。クラスメイトたちが熱を上げているような、著名なアイドルやアスリートより身近に思えたからかもしれない。切り抜きの元動画は削除されていて、その時点で一体何年前のものだったのか、彼がどこの誰かなどはわからなかったけれど。それからしばらく、地元のゲームセンターに通ったりもした。懐かしいな。思春期の一時的な熱などは過ぎてしまえば思い出すことも少ないものだが、今日の出会いはなかなか運命的だと思う。
そんなふうに夢心地のままの帰宅後、思い立って「青柳 e-スポーツ」なんて検索してみたけれどそれらしい人物はヒットしなかった。
▽
一度呼び起こされた記憶は、俺に再び熱を持ってきた。数年ぶりにゲーセン通いにはまって二週間ほど経つ。バイト先近くの小さなゲームセンターで、鈍っていた勘も徐々に取り戻し、気持ちよく遊ぶには困らない。今日もスムーズに連鎖の仕込みを進めていき、あとは最後の一手を待つのみだ。平日昼間の店内には人もまばらで、マッチングした対戦相手の画面はずいぶん鈍い。ばらばらと単発のおじゃまぷよこそ降ってくるが、計画性を感じなかった。もう少しうまい人とやりたいな、なんてちらりと思ったそのとき、待っていた色のぷよが来たので定位置へそれを落とそうとしたが――
「え?」
相手の連鎖が始まり、操作を受け付けない状態になってしまった。チカチカと点滅しながら続けざまに消えていくぷよたち、積みあがっていく連鎖数。
「わーーー!!」
二桁連鎖からの抗いようのない怒涛の量のおじゃまぷよにより、呆気なくゲームオーバーになる。無計画だと思っていた相手の画面は、俺には理解できない技術で構成されていたようだ。このレベルのプレイヤーがこんな場所にいるのか、やっぱり東京って怖い!
「うわあ、相変わらず強いなお前」
「久しぶりだったが、意外と覚えているものだな」
ぐうの音も出ない敗北に放心していた俺の耳に、そんな会話が入ってくる。タイミングからして、今の対戦相手だろう。ひとつあけた隣の筐体にいる強豪の顔を見てやろうと首を伸ばし、そのまま俺は固まった。
「あっ、青柳! さん!」
「え?」
きょとんとした顔で振り返った彼と目が合い、あ、ええと、としどろもどろになりつつ思わず立ち上がる。
「知り合い? 見ない顔だな」
隣に立っていた目立つオレンジの髪色をした男性が青柳さんに訊ねる。口ぶりからして、彼らはここの常連ということだろうか。ということは、やはり変わらずにゲームは続けていたのか。久しぶりと言っていたが、休止明けとか? 憶測がぐるぐると脳内を回るなか、会話をつなげようと焦って口を開く。
「あ、俺はその、昔ゲーム大会の動画で見てて!」
「……あの大会の? それはずいぶん懐かしいな」
すうっと優しげに目を細める彼の雰囲気は落ち着いた大人といった印象で、とても先ほどの容赦ない攻撃を仕掛けてくるようには見えない。喧騒の中においてくっきりとした存在感を見せる彼は、やっぱり目を引く人だと思った。現金なもので、なんだかすっかり長年の熱心なファンみたいな気持ちになった俺は、この時間を引き延ばせないかと思考を巡らせる。握手でもしてもらおうか、なんて思ったとき、ピコン、と通知音が響いて青柳さんの隣の男性がスマートフォンを取り出した。
「あっちの買い物も済んだってよ。そろそろ行くか」
「ああ」
それまで座ったままだった彼は立ち上がり、こちらに軽く一礼して背を向ける。この時間が終わってしまうことにどうしても惜しさを感じていた俺は、あがくようにあの!と声を張った。
「また大会に出る予定はあるんですか? 活動名とかって……」
「いや、すまないがゲームは趣味なんだ。また会ったときは対戦してもらえるとうれしい」
なるほど、プロゲーマーにはなっていないのか。残念だけれど、どこか納得もする。社交辞令とわかっていても、また、と言ってもらえたことがうれしく、俺は浮ついた気持ちで足元の袋を探った。店に入ってすぐ、クレーンゲームで獲得したぬいぐるみだ。
「これ、よかったらこはねちゃんに」
「……こはねに?」
一貫してやわらかい面持ちだった青柳さんが、怪訝そうに眉根を寄せる。あ、やばい。勢いで起こした行動に、汗がじわりとにじみ出る。突然話しかけてきた――それも何年も前の動画についてだ――見知らぬ男がペットの名前を出してくるなんて、それはもう、彼からしたらストーカーではないだろうか。青柳さん本人は穏やかそうだが、隣の男性はこちらへ投げる目つきに警戒が見えてすこし怖い。何か考え込むような様子の青柳さんを軽く押しのけるようにして、彼がこちらへ向かってくる。
「お前、こはねのことも知ってるのか。もしかしてライブに来たことあんの?」
ライブ? 予想外の単語に一瞬思考が止まるが、はっとひらめく。青柳さんはオフライン大会に出るような活動はしていないが、ストリーマーなのかもしれない。ライブ配信に割り込んでくるペットとそれにほっこりする視聴者なんて光景は、よくある話だ。
「あ、いえ。見たことはないんですけど、こういうの好きかと思って。ぬいぐるみで遊ぶかなあと」
段々と彼の生活がわかってきた気がして、手に持ったぬいぐるみをぎゅむりと動かしながら答える。ところが予想に反して、青柳さんは一層眉間にしわを寄せた。
「いや、かわいいものは好きだが遊ぶ、というわけでは……」
「ていうか、人の女に堂々とちょっかいかけるなよ」
「へ?」
今の話のどこに「女」が出てきたのだろうか。何か聞き間違えたかと反芻してみるが理解できず、ええと、と愛想笑いが漏れる。オレンジ頭の彼の睨みはより鋭くなり、うるさいほどに響いていた喧噪が今はどこか遠くに感じる。もしかして俺、ボコられたりするのかな。
「彰人、大丈夫だ。彼もそんなつもりではないだろう。だがすまない、ぬいぐるみなら足りているし、今回は遠慮する」
冷静な声音が割って入ってきて、すがるような気持ちで青柳さんを見る。迷いのない態度でそう言われて、俺はぬいぐるみを引っ込めた。ああ、迷惑なファンそのもののムーブをしてしまった。後悔がじわじわと胸を上ってくる俺をよそに、二人は友人同士らしい会話をしながら立ち去っていく。
「こないだこはねに叱られたんだろ? ベッドの面積がもうないって」
「ああ。次に大物を持ち帰ったら俺の寝床は文字通り床になる約束だ」
楽しげなやりとりの中に決定的な違和感を覚え、あっ、と声が漏れてしまった。耳ざとく振り返った二人に向けて、おそるおそる最後の問いかけをする。
「すんません、もしかしてその……『こはね』って、ペットの名前ではない感じですか……?」
ぱちくり、と音が聞こえそうなくらいゆっくりとまばたきをした青柳さんが、視線を上に向け、斜めにおろし、最後にまっすぐこちらを見据えて口を開く。
「彼女は人間で俺の妻だ」