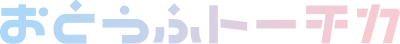ハロー新しい自分、新しい出会い! なんて心を弾ませながら高校へ入学して早半年、ドラマチックな出会いもイベントもないまま過ぎゆく平凡な日常に突然その人は現れた。
「えっ、か、かわいい……!」
思わず声に出た鳴き声みたいな感嘆を、あわてて喉の奥に押し込む。バイトのため急いで帰ろうと昇降口を駆け抜ける俺の目に飛び込んできたのは、他校の制服を着たひとりの女子。目の前に立つ知り合いらしいうちの生徒と話すたびに揺れる羽根みたいなツインテール、まっすぐ相手を見る大きくてまるい瞳。やさしげな笑顔は一方的に眺めるだけで幸福な気持ちになる。
一目惚れって、本当に相手がきらきらして見えるんだ。
電撃を受けたような衝撃にしばらく立ちすくみ、そして彼女の話し相手が見覚えのある人物だと気づいた。
「白石先輩!」
「えっ? あ、放送委員の」
「お疲れさまです!」
びしり、とお辞儀をしてからはっとする。これは中学時代に散々しごかれた野球部式である。あのころの坊主頭はもう封印したのだ。俺はへらへらと取り繕うような笑みを浮かべながら顔を上げた。
「お疲れー。帰るとこ?」
「あっ、はい、バイトがあるんで……白石先輩は」
「私は待ち合わせ中。残り二人と合流して父さんの車に拾ってもらうんだけど――あ、この子はこはね。私の相棒だよ」
こはね! なんと名前も――苗字か?まだわからないが――なんだかふわふわとした印象でかわいらしい、と思ったのも束の間、相棒という単語に思考が止まる。白石先輩って、お笑いとかやってるんだっけ? いや、それなら“相方”か。そもそも、たったいま一目惚れした隣の女の子も白石先輩も漫才をするイメージとは遠すぎる。
「あの、はじめまして」
状況を整理していた脳に響いてきたのは、天国からお届けされているかのような甘い声だった。意識を戻せば、ツインテールの彼女がおずおずといった様子でこちらを見上げてきている。その上目遣い、不安げにカーディガンの袖をたぐっている手元の動作はうさぎやハムスターのような小動物を彷彿とさせる愛らしさだ。
(声までかわいいとか……!!)
短時間での情報過多に倒れそうになりながら、こちらも自己紹介を返そうとし――
「あっ、バイト!!」
ポケットに突っ込んでいたスマートフォンが鳴動したことで、一気に現実へ引き戻される。元野球部の先輩に頼まれて交代したコンビニバイトのシフトは、あと十五分で始まってしまう。引き受けておいて遅刻なんてしたら、あとでどんなしごきが待っているかわからない。俺は心身に刻み込まれた恐怖から、彼女たちへ首振り人形じみた小刻みな会釈を繰り出しながら校門へ走り出す。くそ、運命の出会いだったのに!
▽
「白石先輩!」
「うわっ、びっくりした。君声大きいよね、運動部?」
「今はやってないっす」
翌日、いてもたってもいられなかった俺は果敢にも昼休みに二年の教室へ出向いていた。がらりと開けた扉から呼びかければ、先輩は驚きつつぱたぱたと寄ってきてくれた。委員活動のなかで特別関わりのあるわけではないが、白石先輩は誰にでも親しみやすく接してくれる人だ。昼休みの放送当番もこれまで何度か一緒にこなしたし、邪険にはされないだろうという読みは当たり。これは中学時代に培われた「ヤバイ先輩、まともな先輩」を見分ける力である。
「それであのー、ちょっと相談したいことがあって」
「相談? 私でいいの?」
「先輩じゃなきゃだめなんです、お願いします!」
あっやべ、と思ったときには手遅れだった。すがる気持ちから出た想定外の特大ボイスが教室に響き渡る。まだ始業まで間のある教室はそこまで人が多くはないが、それでも結構な人数の二年生の視線を一斉に集め、俺はその場で直立した。
「おい、入り口でぎゃあぎゃあうるせえぞ」
静かな低音に視線を向ければ、いつの間にか近くに来ていた男子生徒が白石先輩にチョップの振りをしながら話しかけている。着崩した制服に、じゃらじゃらと揺れるピアス。高校デビューを果たしつつも派手なことには手をつけられていない俺からしたら、イケてる上級生のお手本みたいな人だ。
「私じゃないもん」
白石先輩にふい、と拗ねるような態度で指をさされ、それに従って彼の視線は俺へとまった。
「何お前」
「あ、えっと……」
これはヤバイ先輩だ。脳内アラートが瞬時にそう告げる。眉根をぎゅうと寄せて、頭のてっぺんから上履きの先までじとりと睨めつけられ、俺は言葉が出てこない。
「私の後輩なんだからガン飛ばさないでよ、行こっか」
「え、いいんですか」
「いいのいいの」
白石先輩に手を引かれてひやりとしたが、意外にもヤバイ先輩は追いかけてこない。俺に対する剥きつけの敵愾心から白石先輩の彼氏かなと思ったけど、違ったのだろうか。願わくばこの先、あの人と再会しませんように。心の中で十字を切った。
「それで、相談って?」
飲食禁止のため昼休みは人気のないPC室で腰を落ち着け、白石先輩はまっすぐとした目で訊ねてきた。
▽
白石先輩の相棒たる「こはね」さんに一目惚れしたこと、どうにかしてお近づきになれないかということを素直に話すと、先輩はそれを好意的に受け止めてくれた。曰く、こはねは最高にかわいいからね! 見る目あるじゃん! とのこと。聞けば彼女は今のところ恋人なし、好きな人もおそらくなし。私からこはねに押し付けることはできないけど、とりあえずもう少し話してみる? と、今日の放課後また昇降口で待ち合わせしていることまで教えてくれた。これはもしかして、天が俺に味方してくれているのだろうか。ハロー、新しい出会い!
浮かれた気持ちで午後の授業を終え、トイレで念入りに身だしなみを整える。かつての坊主頭はいまや明るい茶色に染まり、長めに伸ばした髪はしっかりセットも決まっている。白石先輩たちはストリートを中心に音楽活動をしていて、その相棒関係なのだということも聞いた。付け焼き刃にも程があるが、動画サイトで有名どころの楽曲チェックもした。こはねさんのかわいらしい雰囲気からは想像もつかないジャンルで少し意外だったが、ギャップというのもいいものだ。
ワックスでべたべたになった手を丁寧に洗い、逸る気持ちをなだめながら階段をくだっていく。ずらりと並ぶ学年ごとの靴箱と傘立て。本来他校生はここまで入ってこないのだけれど、雨の日に待たせることもあるからと昇降口で落ち合うのが決まりになったそうだ。靴を履き替え、扉付近をぐるりと見回す。
――いた!
忘れもしない、昨日見たばかりのツインテールとセーラー服。何枚も並ぶうち締切になっている扉に背中をあずけ、校舎内側を見るともなくみつめているこはねさんが視界に入った。時々ちらりとスマートフォンを確認したり、鞄についているマスコットをむにむにと握ったりしている。その様子もなんともかわいく、感激しながら心のアルバムに保存した。しばらく待ってみたが伝手である白石先輩はまだ現れず、一人で話しかけてしまうか迷っていると、不意に背後から誰かが俺を抜き去っていった。
「小豆沢」
「青柳くん! お疲れさま」
顔を上げたこはねさんは、声の主を確認してぱあっと表情をあかるくする。青柳と呼ばれたその人もまた、柔らかな表情で会話を続けてゆく。あ、これって先輩が言ってた「あと二人の仲間」のひとりか。残るひとりはあのヤバイ先輩あらため東雲先輩だと聞いている。
「杏ちゃんたち、もう少しかかるみたいだね」
「ああ。まったく、どうしたら小テストの追試なんてことになるんだ」
白石先輩、来ないと思ったら追試中なの!? がくりと膝が落ちそうになるのをこらえ、二人の会話を盗み聞きする。こはねさんの様子は昨日白石先輩と話していたときと似た感じだ。青柳先輩もまた彼女にとって気兼ねない友人なのだろう、俺に見せた人見知りっぽい態度とは違ってリラックスしているのがかわいらしい。俺もあんなふうに笑いかけてほしいものだ、と妄想する。
「苦手な単元だったら仕方ないよ」
「その苦手が多すぎる」
「じゃあ、またみんなで勉強会しよっか」
「そうだな」
ふふ、と微笑んだこはねさんに答えた青柳先輩の表情を見た瞬間、俺は二人の関係性を察した。察せてしまえたのだ。だって、俺も彼女を好きだから。
青柳先輩は怜悧な印象を与える切れ長の目をすうっと細めて、愛しむようにこはねさんを見ている。よく見れば彼はこころもち背を丸めていて、小柄な彼女の言葉を聞き逃すまいとしていることがうかがえる。一方でこはねさんはぴんと背を伸ばし精一杯近づいて話していて、なんというか。二人の醸す空気も印象も、はじめからそうおさまるように神様が用意したみたいにお似合いだった。
ここへ割って入っていくのはだいぶ厳しい。このあと白石先輩が来て俺を紹介してくれたところで、だ。なるほど確かに、こはねさんには好きな人がいないのかもしれない。でも、こはねさんを好きな人が近すぎる。ここは一旦、仕切り直しだ。俺は心を決め、なるべく二人から離れた扉を選んで外へ出る。ていうか、青柳先輩がライバルだとして自分に勝ち目って?
こはねさんとすでに親しく、誰が見ても認めるだろうきれいな顔立ちに、あの落ち着いた態度。たぶん頭もよさそうだ。この時点で相当にスタート地点が不利である。はああ、と大きくため息をつき、でもあきらめたくないなあと天を仰ぐ。とりあえず、彼の情報収集から始めようか。