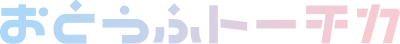「彰人、お前も俺の顔がいいと思うか?」
「ぶっ」
週明け月曜日の昼休み、うしろの席の杏は委員会のため不在で、ちょうどいいので冬弥をそこへ座らせて昼食をとっている。さすがに一月に寒風吹きすさぶ屋上には出たくないからだ。食事もそこそこに何やら真剣な表情でスマートフォンを眺めていたので、調べものでもしているのだろうとそっとしておいた相棒から飛んできたのは、突拍子もない問いかけだった。彰人は咀嚼中のサンドイッチが杏の机にぶちまけられなかったことに安堵しながら、注意深く飲み込む。
冬弥が誰に何を言われたのか、思い浮かぶ顔がひとつあった。詳細は聞き出せなかったが、土曜日に絵名と偶然の関わりがあったらしいことを聞いている。そこで妙なことを吹き込まれたのかもしれない。姉は冬弥のことを「本当にいい子」と評し、さらに冬弥と一緒にいたというこはねにも言及していた。小豆沢さんもすっごくいい子、と。
「そうだ、お前一昨日こはねと何してたんだ?」
昨日四人で集まったときにそんな話題はひとつも出なかった。ハードな練習に揉まれてすっかり訊ねるのを忘れていたが、貴重な休日にわざわざ二人が会う用事なんてあったのか。深掘りするのも野暮なことかという気遣いが一瞬よぎるが、彰人たちに隠すようなことであれば絵名にも口止めするだろうし、だから聞いても構わないはずだ。質問に別の質問を投げられた冬弥はなぜだかこくりとひとつうなずき、画面を見せながら答えてきた。
「協力し合ってフォトコンテスト用の写真を撮っていた。これなんだが」
「……え?」
そこに表示されていたのは、ファッション誌よろしくポーズを決めている相棒の写真だった。じっくり見る前にすいっとスワイプされていき、全部で三枚あることだけは理解した。
「入賞の目的は果たしたし、賞品もバレンタインまでに届くらしいから本当によかった。ここのチョコ、彰人が以前また食べたいと言っていただろう」
「ちょ、っと待て待て待て情報が多い。なんだこの……化粧もしてんの?」
「あーっ!! やっぱりそれ青柳くんだよね!?」
混乱する彰人の横から大声で割り込んできたのはクラスメイトで、ほらやっぱり! と周りに手招きまでしている。なんだこれ、面倒そうだな。彰人は瞬時にそう判断し、ちょっと来い、と冬弥をつれてそそくさと教室を出た。
▽
「つまり、その限定品のためにこはねも絵名もコンテストに参加してたのか」
結局、ひと気を避けてたどりついたのは屋上だった。今日の最低気温はマイナス一度、未明には都下で雪もちらついたらしい。彰人たち以外の人影がないなかで、寒さを気にする様子もなく週末のできごとを楽しそうに話す冬弥の鼻先は心なしか赤い。
「ああ、ものすごい偶然だったな。それに、みんな狙っている賞品は分かれていたから勝ち負けはあっても円満に終えることができた」
いい経験だった、と結びうれしそうな顔を見せた冬弥は、それで、と話を切り替えた。
「順位は『いいね』の数で決まるんだが、コメントもつけられるんだ。何か参考になることがあるかと思ってずっと読んでいて」
「参考って、またモデルやる気か?」
「そういうわけではないが、見せ方や見え方はライブのパフォーマンスにも通じると思う」
「それはまあ、確かに」
人生の経験値が一般的な同世代より少ない、ということを常に気にしている冬弥は、過剰なくらいにあらゆるできごとから学びを得ようとする。かといって、それが無理をしているのかといえばそうでなく、楽しんでいるのだから恐ろしい奴だ、と彰人は思う。
「だが、一番多いのがこの言葉なんだ」
再びこちらに向けられた画面に映っていたのは、いかにもSNSらしい短絡的なコメント群だ。
『顔がいい』『顔がいい人は顔がいいなあ』『メイクとか構図もこだわってるのは感じるけどとにかく顔がいい』
「俺は顔が『いい』のか?」
発言者が彼でなければとんでもない嫌味に聞こえそうだが、冬弥はあまりにまっすぐな目をしている。彰人は軽く肩をすくめて事実を口にした。
「お前は見映えするよ。分類するなら塩顔系じゃねえ?」
「塩」
「そう。そしてオレならしょうゆ」
「そんな……人の顔をおせんべいみたいに」
「オレもなんだよそれとは思ってるけど、雑誌なんかには誰でも知ってることみたいに書いてあるだろ」
いつだったか、二人はタイプが違うからバランスいいよね、と顔見知りのミュージシャンから何気なく言われた記憶がよみがえる。声質だとか顔タイプだとか、そういうのはばらけていたほうがウケがいいんだよ、と。
「……これはただの興味で訊くんだが」
「ん?」
「小豆沢や白石はどう分類されるんだ? 砂糖やクリーム……か?」
そうきたか。脳内にカフェドリンクよろしくデコレーションされた女子二人が浮かび、笑いそうになりながら訂正してやる。
「ええと……あいつらはあれじゃね? 杏なら猫顔、こはねはたぬき顔」
「女性は動物なのか……そして小豆沢はハムスターにはならないのか」
「いやわかんねえよ、オレもそこまで詳しくねえしやめやめ」
自分たちだけならともかく、女子の外見について話していたなんてことが知られたら厄介だ。彰人は話をそこで打ち切って、戻ろうぜと踊り場へ続く扉を開ける。昼休みはもう五分も残っておらず、教室へ戻るべき時間だった。
「塩……」
背後からぼそりと聞こえてきた声に、下手にこの表現で説明しないほうがよかったかと反省する。冬弥はきっと、明日にはイメージコンサル関連にものすごく詳しくなっているだろう。
「あのな、訊きたかったのはそこじゃねえんだろ。お前は顔がいいよ。多分、大抵の奴から見て」
正直なところ、見映えのよさはあって困ることはない。ストリートに足を踏み入れてすぐ冬弥の噂が彰人の耳に入ったのだって、要するに外見も含めて総合的に目立っていたからだ。もしも相棒がこれを機に武器のひとつを自覚して活用してくれるなら、悪いことではない。実力で上に行くにしたって、フックは多いほうがいいのだ。
「ていうか、これまで誰からも言われなかったのか?」
「容姿の評価なんてされる機会もなかったからな」
神妙な面持ちでそうつぶやいた冬弥は、一拍置いて言い直した。
「いや、気にする機会がなかったのか」
「その言い方だと、今は気になってるのか」
「……どう見られているのか、程度には」
へえ、と彰人は意外に思う。環境と本人の性格からだろう、身だしなみは隙がないが洒落っ気もない冬弥にも、それくらいの自意識はあったのか。そんな風に思っていると、冬弥はどこか自嘲じみた笑みを見せた。
「しかしこれだけコメントで褒めてもらっていても、肝心な人に響かないなら意味は薄いな」
「まあ、万人受けする見た目なんてそうそうねえだろ。好みにあわなきゃどんなに整ってようが眼中にねえよ」
「眼中に……そうだな、レンズ越しとはいえあれだけ見つめあって何もないなら、そうなんだろう」
「そーそー」
階段を下り、彰人はそのまま自分の教室へ向かう。冬弥のクラスは反対方向だ。また放課後な、と軽く振り返って別れを告げ廊下をしばらく歩くうちに、先ほどの冬弥の言葉に覚えたひっかかりの正体に気づく。
「レンズ越しに目が合ってたのって――え?」
ほんの数十分前に教えられたフォトコンテストのサイトを、検索して開く。結果発表と書かれたページの中ごろに、相棒の写真が堂々と載っている。“いちばんよく撮れた”と言っていた三枚目はいかにも瞬間を切り取ったといった自然な笑顔だが、他の二枚はじっとこちらを――シャッターの向こう側の存在を――見つめていた。
「マジで?」
彼がこの写真に、カメラマンであるこはねに響かせたい思いを乗せていたのだとしたら。それはなんとも――
「バレンタインかあ……」
その味わいは、スイートにもビターにも振れる。よくできたイベントだと、彰人は心中で相棒にエールを送った。