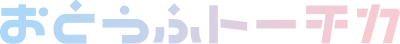お、また来てる。プライズの補充とレイアウトを済ませてガラスケースの鍵をしめながら、私は目の端に常連の姿をとらえていた。この近くにある都立高校の制服をきっちり着こなし、ごちゃついたゲームセンターにはすこし不釣り合いな雰囲気の男の子。彼がここに顔を出す時間帯は大きく二つだ。授業が終わって寄り道に来たんだろうなという夕方、そして塾かバイトか、何かしらの用事を済ませた帰り道らしい夜八時過ぎだ。
春から入社したゲーム関連会社はアミューズメント展開もしていて、新人は採用職種にかかわらずしばらく店舗で接客に従事する。それが向いていなくてやめてしまった同期もすでに何人かいるが、私はいまのところストレスには感じていない。こうやって、目をひくようなイケメンをみつけて観察することもできるし。
「あの、すみません」
「はい! どうされました?」
自分の世界に入り込んでいた私は、突然話しかけられてびくりと体を揺らす。目の前に立っているのは例の彼だ。ここまで近づいたのは初めてで、背もけっこう高いな、と自分の目線を基準に計算する。180ないくらいかな、細身だから実際はもうちょっとあるかもしれない。
「そこの機体にお釣りが残っていて……」
「ああ! すみません、ありがとうございます」
困ったように百円玉を三枚渡され、私は礼を言う。前の利用者が五百円玉で一プレイだけしていったのだろう。こんなの取りにくる客などいないし、かすめ取っても誰もわからないのに。律儀な、いや、善良な子だなあと思う。
「あ、そうだ。ぷよぷよアプデ入りましたよ、お時間あったら遊んでみてください」
「え? あ、はい……ありがとうございます」
さらに一段、困惑顔を深めた彼に、私は自分の失敗を悟る。しまった、こちらが勝手に認識していただけなのにまるで知り合いみたいに話しかけてしまった。
そう、彼を覚えていたのは何もその目立つ容姿だけではなく、ゲームの腕前でだった。いわゆるガチ勢は平日の昼間でも何時間もはりついてプレイしていることも珍しくないが、彼は頻度こそ高いがふらりと入ってきて一時間も滞在しない。なのにものすごく上達が早いし、色んなジャンルのゲームを試している。それでいて、表情は常に固くあまり楽しそうには見えない。はじめはゲームセンスに注目していたけれど、最近は保護者じみた目線ですこし心配しながら見守っている。深夜までいるわけでもないし、考えすぎだといいのだけれど。
迂闊に話しかけたせいで困惑させてしまったな、と反省しつつ、素直にぷよぷよをプレイしてから店を出ていく姿を見て私はくすりと笑う。無愛想ではあるが、なんというか、いい子である。
▽
おー、来てる来てる。私はにやけそうになる頬に力を込めて平静を装う。相変わらず隙なく制服を着こなして訪れる彼は、最近よくひとりの女の子を連れている。そのすこし前からはにぎやかな四人組で遊びに来ているのを見かけるようになっていて、それに伴って彼の表情はだいぶ豊かに、やわらかくなっている。心許せる友人ができたんだな、と外野ながらもほっとした。そのころには顔見知りの店員、くらいの認識を彼からもらっており、たまに二言三言交わすようにもなった。そしてさらに数カ月経ち、私は密かに彼の恋路を応援している。
店からすこし離れた地区にある女子校の制服姿をした彼女は、ひとことで言うとかわいらしい子だ。彼同様、素直そうないい子である。はじめのころは二人でいても会話が弾む様子もなく、こっそり聞き耳を立てた範囲でわかったのはどうやら女の子がクレーンゲームのコツを教わっているらしい、ということ。習い事に励むように真剣な指導と練習を行う彼らは、上達とともに距離を縮めていった。
つい先日は恋人でないとあり得ないレベルの近い距離感で話し込んでいるのを見てしまい勝手に気まずくもなったけれど、どうやらまだお友達、らしい。でも、彼女は遠目で見てもわかるくらい彼にきらきらした瞳を向けているし、それを受け止める彼もまた満たされた顔をしている。わかるよ、いちばんもどかしくも楽しい時期ってやつ。
それから季節が巡りあたらしい春がそろそろ、というころ、彼は真剣そのものの表情でひとつのプライズと向き合っていた。そんなに難しい設定にしたやつあったっけ? と不思議に思いのぞきこむと、特に人気商品でもない、どちらかというとニッチなへびのぬいぐるみだ。設定金額も大したことないし、だいいち彼の腕なら三クレジット程度で取れるだろう。
「それ、難しいかな?」
思わず話しかけると、彼は珍しく焦ったような様子でいえ、と首を振る。
「いちばん似ているのを獲りたくて」
似ている? 何に? 疑問は解消されなかったが、それからたっぷり三十分、彼はその筐体前で悩んでいた。最終的にはこれと決めたらしい個体を見事なアームさばきで獲得し、大事そうに袋へしまい満足気に去っていった。
そんな光景を目にしてからひと月も絶たず、私は辞令が出て本社へ異動となったのだった。
▽
「あ、久しぶり」
「……どうも」
一年後、本社からのチェックという立場で懐かしの店舗へ顔を出した私は、偶然にも制服の彼と出会った。まだ高校生ということは、今三年生か。彼は店員の目印たるエプロン姿ではない私に一瞬気づかなかったが、すぐに思い出したようでぺこりと頭をさげた。
「今日はひとり? 相変わらずたくさんゲットしてるね」
両手にさげたビニール袋には、相当な量のお菓子が詰まっている。
「はい。俺はそんなに食べられないんですが、友人たちがもらってくれるので」
高校生といえば、お小遣いやバイト代をやりくりしている年頃だ。ただで配ってくれるならありがたいに決まっている。そういえば、彼はいつも金額に無頓着で遊んでいたな。性格からして人気のプライズを転売しているってことも考えにくいし、裕福な家の子なのだろうか。これまで感じ取っていた雰囲気からも、なんとなく納得する。
「いいねえ。彼女さんもよろこぶでしょ」
「彼女……」
「ほら、ツインテールのかわいい……」
そこまで口に出して、あ、と固まる。記憶も曖昧になっていたせいで未確定だった情報で話してしまった。ええと確か、よさそうな雰囲気で、両想いっぽくはあった、のだけれど――
「付き合っていたことなんてありませんが」
感情のない声と、何も悟らせない無の表情で彼は答えた。どうしよう、お客のプライベートに踏み込んでしまった。それもおそらく、かなりまずい結末の。自分のやらかしに一瞬気が遠くなっているあいだに、彼は素っ気なく私の前から去っていった。うう、苦情を言われたほうがましである。
それにしても、あんなにいい感じだった二人でもうまくいかないことってあるんだな、と思春期の読めなさを思い出す。彼は否定したが、もしかしたら一度は付き合って、だめだったのかもしれない。恋愛とはむずかしいものだ。
でも少年、それもいつかはいい思い出になるよ、なんて大人を通り越して老人じみたことを考えながら店の外に目をやると、そこにはかつて見慣れた彼ら四人が歩いていた。どうやら一緒に来ていたらしい。んん? と腑に落ちない気持ちになる。あきらかにうまくいかなかったっぽい恋の相手と、今もつるんでいるのか。会話は聞こえるはずもないが、賑やかにおしゃべりしながら通り過ぎていく。ツインテールの彼女は相変わらず彼ににこやかに話しかけるし、彼も微笑み返している。
……なんで?
先ほどの、氷でも降るんじゃないかと思わせる態度とあまりにも結びつかない。わからない、高校生、怖い!
私のそんな混乱は、さらに五年ほど経ったころにネットニュースで見かけた、人気ストリート音楽ユニットから二組同日の結婚発表!という記事に彼らの写真をみつけたことでますます深まるのだった。