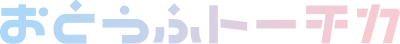どういうつもりか知らないけど、私の可愛い相棒を悩ませるなんて許せない!
憤然とした気持ちで、杏は冬弥のクラスの前で待ち伏せをするべく急いで教室を出た。座席がどこかは知らないが、前方にいたら確実に邪魔だしきっとうしろのほうだろう、と考えて後方の扉の横で仁王立ちする。中から漏れる終礼の音を聞いていると、廊下の向こうになじみの顔が見えた。
「……何してんの?」
「待ち伏せ」
短く答えた杏の言葉に、やってきた彰人は怪訝な表情を変えず質問を重ねる。
「誰を」
「冬弥くらいしかいないでしょ」
「いやお前の交友範囲なんて知らねえし」
ぼそりとつぶやきながら順番待ちよろしく隣に並んだのがなんだかおかしくて、杏は思わず笑いそうになったがあわてて頬を引き締めた。こいつは何かあれば絶対に冬弥の味方をするはずだ、油断してはならない。
「でも珍しいな、メッセージじゃ済まない用事か?」
済まないからここにいるのだ、と気持ちをこめて深くうなずく。ついでに拳を強く握りしめてみせた。
「今日は練習もないし、たっぷり話を聞こうと思って」
「あ、オレちょっと用事思い出したから帰るわ」
面倒ごとの気配を察知した彰人が場を離れようとするのを、止めるべきか見逃すか一瞬迷ったそのとき、がたがたと椅子を引く音が廊下まで響く。と、ほぼ同時にがらりと扉が開いた。顔を出した一人の男子生徒は、杏たちを一瞥してから振り返って教室内に呼びかける。
「青柳、相棒くんたち待ってるぞ」
「たち?」
不思議そうに聞き返しながら姿を見せた冬弥は、二人をみとめるとすぐ納得したようにうなずいて扉の外へ歩いてきた。
「二人とも、また補習か」
「ちげえよ、仮にそうだとしてなんでそろってお前に報告しに来ると思うんだよ」
「言われてみればそうか」
「ちょっと冬弥、ツラ貸して」
放っておいたらきりがなさそうな呑気なやり取りに割り込み、杏は手ぶりでついてくるよう示した。冬弥はチームの活動絡みの話だと思っているのだろう、特に何か訊いてくることもなく三人でぞろぞろと歩き出す。目的地は決めていなかったが、こういうときセカイの存在は本当に便利だ、と思いながらスマートフォンを取り出した。
▽
不安そうにうつむいたこはねから、青柳くんに避けられているかもしれないの、と相談されたのは昨日の練習後のことだ。喧嘩をしたのかと訊ねると、そんなことはないと言う。
彼女が冬弥に静かな恋愛感情を抱いていることは以前こっそり打ち明けられていたが、いまのところ伝えるつもりはないと聞いていた。だから杏もとくべつな行動は起こさなかったし、何より最近はチームとしての活動が順調で、そういうことまで気を回していられない。そんな中で、二人の間にどんな歪みが生じたのだろう。話を促すと、こはねの中でもまだ確信に足りないのか、違和感をひとつずつ確かめるように口を開いた。
このところ、練習に絡んだ必要最低限の会話しかしてくれない。訊きたいことがあって話しかけても、距離をとられている気がする。二人きりになるといつの間にか姿を消してしまう。何より、目が合うとあからさまに顔をそむけられる。
もしかしたら私の気持ちがばれちゃって避けられているのかもしれない、今までみたいにチームメイトとして仲良くできないのかな、と悲しげにつぶやいたこはねを思い出すだけで心が痛む。もし本当に冬弥が彼女の気持ちを察して疎ましく思っていたとして、無言で避けるなんてひどい話だ。こはねは失恋くらいで折れる子ではない、迷惑ならこそこそ逃げずに言ってやるべきだと思う。尤も、彼が彼女を鬱陶しがるなんて構図は、杏が見てきた二人の関係を思うと違和感が強い。そこも含めて、はっきりさせたかった。
憤りを抱えながらセカイへ来たものの、他にあてもないのでいつものようにメイコのカフェへ入る。ドアベルの音と並んで聞こえたいらっしゃい、という迎えの声を耳に、ひと気のない店内を進み奥のテーブル席で二人と向かい合う。各々で飲み物を注文し終えると、冬弥はちらりと入り口へ視線を投げながら口を開いた。
「小豆沢も来るのか?」
「今日は来ないよ」
そっちから名前を出すとはいい度胸じゃない、と脳内でファイティングポーズをとる。けれど、そうか、とちいさくこぼした冬弥の表情がどこか残念そうに見え、杏は考えていた詰問の順序を飛ばしてしまう。
「こはねのこと避けてるんじゃなかったの?」
直球すぎたかな、と思うが勝手に考え込むより目の前の本人に訊いたほうが早い。駆け引きを要する複雑な思考に向いていないことを、杏は自覚している。
わずかな間のあと、冬弥は気まずそうに視線を泳がせてから控えめに首を揺らした。
「その傾向はあるかもしれない」
本人からの証言を得て、杏は覚悟していたよりも強いショックを受けた。これまで散々、チームは仲良しこよしじゃないと恰好つけたことを言っていた彰人も真向かいで目を瞠っている。飲み物を運んできたメイコは、空気を読んだのかすぐバックヤードへ引っ込んでいった。タイミングわるくBGMも一旦途切れ、数秒の静寂が場へ落ちる。
「それは、どうして……?」
こはねを曇らせていることへの文句を言ってやろうと思っていたのに、いざとなるとか細い声しか出てこない。昨日まで信じていたものが崩れていく感覚に、口の中が乾く。無意識に見やったアイスティーのグラスは、涼しげに汗をかいていた。
「その、小豆沢が」
「こはねが?」
「か」
促されるがままに答えていた冬弥が、喉に何かがつかえたようにそこで動きを止めた。言い淀んだまま、ちらりと彰人を窺っている。やはり事情を知っているのかと疑いを込めた視線を投げると、彰人は冤罪だと言わんばかりに眉間に皺を寄せた。
「冬弥、言いたくねえなら言わなくてもいいんだぞ」
「ちょっと、勝手にそんなこと」
「いや、そういうわけではない。どう表現しようか迷っただけで」
彰人に抗議しかけた杏を手ぶりで制し、冬弥が口を開く。彼が説明に迷うほどのことなのか、となんだか難しげな気配を感じて居住まいを正した杏の耳に、聞こえてきたのは予想を超えてふにゃふにゃとした回答だった。
「小豆沢が、最近可愛くて……」
「は?」
杏と彰人の呆気に取られた相槌が見事にユニゾンする。質問と回答があっていないような気がして、一度胸中で復唱した。どうしてこはねを避けているのか。最近可愛いから。最近?
「何を今更なこと言ってんの、こはねは出会ったときから最高に可愛いじゃん。今まで目つむって生きてたの?」
「そんなことはないはずだが」
「おいその流れ一旦やめろ」
身を乗り出した杏の目の前に、骨ばった手がひらひらと舞う。いつの間にか立ち上がっていた彰人が、その場を仕切り始めた。
「喧嘩したとかじゃないってことだな?」
「もちろん。これは俺自身の問題だ」
先ほどまでの逡巡は何だったのか、きっぱりと言い切ってついでにちょっと胸も張っているような気がする冬弥の態度に、杏は余計にわからなくなる。
「小豆沢と接していると、会話をするにもまず可愛いな、と見とれてうまく受け答えができなくなってしまった」
これには俺も困っているんだ、と表情だけならなにごとかと思わせる憂いを帯びる冬弥を、彰人はしばらく無言で見ていた。ふ、と一瞬天井に視線をやり、細く息を吐きながら座り直す。
「解散していいか」
「だ、だめだよ! 解決してないじゃん!」
入れ替わりに思わず立ち上がった杏へ、彰人はごくまっとうな言葉を返す。
「じゃあ解決してみろよ、どうすんだよここから」
「冬弥の行動の理由はわかったけど、そのせいでこはねが悩んでるの! 今言ったことをちゃんとこはねにも説明するか、克服していつも通りに戻るかしてよ」
「いや、説明ったってお前それしたら」
勢いでまくし立てたものの、杏だって気づいている。この冬弥の心情を説明するということはつまり、告白しろと言っているようなものだ。杏はすでにこはねの気持ちを知っている。だからそれで丸くおさまるじゃん、という考えになるが冬弥と彰人は当然知る由もない。それに、チーム内の空気を思えば、二人がこの想いを隠したまま時が過ぎていくだろうことは想像がつく。
でも、せっかく両想いなのに!
うう、と途方に暮れその場で足踏みをする杏の心中などお構いなしに、馬鹿正直に先ほどの言葉を咀嚼していたらしい冬弥が口を開いた。
「説明、か……もうすこし自分の中でまとめてみるか。今まではあまり友人がいなかったから、女子に苦手意識があるなんてはじめて気づいたんだ」
「は?」
「ちょっと待てお前、女子で括るな女子で」
想像を遥かに超えた謎理論の展開にぽかんとする杏を置いて、彰人がぎりぎりのところで突っ込みを入れた。彰人お母さん、あとはよろしく。力なく腰をおろしながら、杏は理解ある相棒くんにすべてを託すことにした。
「なぜだ? 彰人と小豆沢の違いを考えたらまずはじめに性別がくるだろう」
ここ――セカイで話しているという意識も手伝ってか、いまの冬弥の世界にはどうやらチームメイトたちしかいないらしい。相棒か、それ以外か。そんなフレーズが杏の脳裏に浮かんで消えた。
「ベン図がでかすぎんだよ! じゃあこいつ見てみろ、同じように落ち着かない気持ちになるのか!?」
「へっ、私?」
力を抜いたところにびしりと音が出そうな指差しとともに水を向けられ、素っ頓狂な声が出る。冬弥もなぜだかおどろいたような顔をして、杏へ視線をよこした。
「白石に? 考えたことはなかったが、そうだな……」
見定めるようにじっとみつめられ、杏は無意識に息を止めた。怜悧な印象の双眸が自分を検分しているのを感じながら、そういえば入学してじきのころ、冬弥と知り合いであることを他の女子生徒にうらやましがられたこともあるなあ、と思い出す。著名な親と整った容姿をもつ冬弥は、進学で人間関係のリセットされた新一年生のなかでもわかりやすく目立っていた。
杏だっていわゆる美形を見ればそれなりに沸く気持ちもあるが、はじめて紹介されたときも彰人が相棒に選んだ子、という認識のほうが強かった。なにより、同い年で伝説の夜の話ができる貴重な相手だった彰人――今思うと別人みたいに猫を被った、まだこちらを苗字呼びしていたころ――のことをちょっとだけいいな、と感じていた当時の杏の眼中に冬弥は映っていなかった。チームを組む前のひと悶着により一旦霧散したささやかなこの感情については、誰にも打ち明けず墓場まで持っていくと決めている。
「とくにそういう気持ちにはならないな」
過去に思いを馳せているうちに、冬弥は杏から視線を外し平坦なトーンでそう言った。時々思うが、デリカシーのなさは彰人より冬弥のほうがひっかかることがある。姉がいる彰人はぶっきらぼうなようでいて案外、そのへんの機微を読む。
「別にいいけどちょっと腹立つ」
「いやすまない、白石も可愛らしいぞ。なあ彰人」
「オレに振るな」
冬弥の言葉をはじき返すように、しっしと手を振って彰人は閑話休題とばかりにストローを咥える。ひと口、ふた口と飲み下してグラスを置き、杏と冬弥の二人がその挙動をじっと見て待っていたことに気づくと居心地わるそうに肩を回した。
「で、こいつは平気でこはねがダメってことは女子とかそういう話じゃねえだろうが」
「そんなことは……白石は、付き合いも他より長いから」
「お前さ、こはねが特別になった、って思いたくねえからごまかそうとしてるだろ」
「……」
杏が踏み込めなかったひとことを、彰人は静かに突きつけた。妙な言い回しに翻弄され、もしや恋心の自覚がないのかと思いかけたが要するにそういうことだ。先ほどから冬弥はわざわざ問題の対象をひろげて、こはねと向き合うことを避けている。彰人の言葉に気まずそうに瞳を伏せる様は、とっくにばれているいたずらを隠し通そうとするこどものようだった。
ふと、こはねから彼への想いを聞いた日のことを思い出す。あのね、青柳くんのこと、好きになっちゃった。まるで犯した悪事を告白するみたいに切り出した彼女の表情は、目の前の冬弥と重なるところがある。
恋バナなんて、もっと気軽にできるもののはずなんだけどな。
せっかく出会ったのに、否、出会ってチームを組んだからこそ複雑な事態になってしまった二人に同情を覚えつつ、杏は氷ですっかり薄まってしまったアイスティーを口に含んだ。