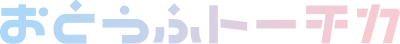小さな箱というのはおもしろいもので、毎日かわるがわるやってくる演者ではなくライブハウスそのものにファンがついていることも多い。オーナーのセンスに心酔している者、見知った客同士の憩いの場として通う者、一体どこから仕入れているのか、その店にしかないマイナーなクラフトビールを求めて来る者などさまざまだ。
そういったある種の閉じた世界でひとつずつ認められていくのも大切なことだが、同じ場所に居続けると視野が狭くなる。だから彰人はなるべく多くの人脈をつなぐようにしているし、どこでも誘われれば積極的にステージに上がる。
そんな流れで、ビビッドストリートから足を伸ばした、ライブハウスや小劇場がひしめく隣町の一角に今日は来ていた。初見の観衆の反応が二週間前、ひと月前、半年前よりも盛り上がっていると感じられると達成感があるものだ。
そのかわり、面倒に思うこともある。彰人はロビーの人だかりをひとつ挟んだ向こう側で、今日はじめて共演したミュージシャンに道をふさがれているこはねを眺め、どうすっかなあ、とため息をついた。まじめな話をしている可能性もあるが、相手のへらへらした表情からしておそらくただのナンパである。ビビッドストリートにいるときはほとんど起こらない――何しろ、謙の娘である杏が溺愛する相棒で、さらには大河にも目をかけられている存在だ。後先考えずちょっかいを出すのは、よほどの新参者くらいしかいない――のだが、余所に出ればこういうこともある。杏はというと、すぐうしろで父親の顔見知りだというベテランのチームに声をかけられて昔話で盛り上がっている。
別にライブハウスの風紀がとくべつ悪いわけではない。ただ、街中ですれ違うよりは声をかけやすいのだろうと彰人は思う。ここにいる人間、更に演者同士なら話題が通じやすいことは明白だ。場の高揚感も手伝って、ふだんに比べたら出逢いに積極的になるのは不思議ではない。
「すみません、明日も学校があるんでこのへんで」
親戚のおじさんよろしく杏の頭をわしわしと撫でようとした男性の手を遮ってそう言うと、そんな時間? と呑気に見上げられて彰人は眉間に皺を寄せた。こいつはこいつで、謙の娘という防犯札がどこででも通じるわけではないということを、果たして理解しているのだろうか。
「あっちでこはねが絡まれてるぞ、回収してこい」
「絡まれて……? 冬弥もいるじゃん、大丈夫じゃない?」
「え?」
振り返って先ほどの場所に視線を戻すと、いつの間にかこはねの隣に冬弥が立っていた。合流するべく近づいていけば、ちょうど推定ナンパ野郎が立ち去るのとすれ違う。
「彼氏こわ」
小さくつぶやかれたそれは事実とは異なる誤解なのだけれど、そう思われても仕方ないよなあ、と澄ました顔でこはねの横に仁王立ちしている相棒を見て半ば呆れながら思った。
▽
「お前のそれって自覚してやってんの?」
迎えが来るという杏たちとライブハウスの前で別れた帰り道、彰人は何の気なしに訊ねた。シブヤまで電車に乗ってもよかったが、近いくせに各駅停車で四駅もかかるのでぶらぶらと歩いている。それにライブのあとはなんとなく、外気にあたっていたい気持ちもある。
「どれの話だ」
「後方腕組み彼氏面」
「彰人はおもしろい言葉を使うな」
「とぼけんなよ」
冬弥の反応に、こいつわかっててやってるなと確信して冗談まじりに強めの返しをする。しかし、冬弥は眉ひとつ動かさずに首だけ傾げた。
「……小豆沢に対する態度のことを言っているなら、彰人が思っているようなことはないぞ」
「は? 嘘だろお前」
思わず声が裏返りそうになるのを既のところでおさえて聞き返す。彰人に教えるつもりがない、ということだろうかと思ったが、続く言葉は不可解なものだった。
「認めろというなら認めてもいいが……いいのか?」
それほとんど肯定してるだろ、と出かかった突っ込みを飲み込んでまじまじとその顔を見る。こちらをからかうとか煙に巻くとか、そんな印象は持てないごく真剣な目をしているので余計にわからない。ふと、もしやと思った懸念を口にした。
「いちおう言っておくが、別に恋愛禁止とか掲げてねえからな」
「ああ」
どうやらこれは空振りらしく、うすい反応とともに会話が一旦途切れた。居酒屋や二十四時間営業のスーパー、シャッターを下ろした個人商店などがランダムに並ぶ目抜き通りは、二人の影を消したり伸ばしたりする。駅前へ続く道を左にそれると途端にひと気がなくなり、自分たちの靴音が妙にくっきりと聞こえる。
「俺は最近、自分を客観視するよう意識しているんだが」
話題を変えようとしたのか、不意に冬弥が語りはじめたので彰人は取り出しかけていたスマートフォンを再びポケットの底へ落とした。
「ん? おお、いいんじゃねえの」
出会ったばかりのころと比べてずいぶん柔軟になったよな、と続きは声に出さずうなずく。とくに、四人で活動するようになってからはそれが加速しているので、やはり表現力や可能性を伸ばす意味でもチームを組んで正解だったと思える。
「小豆沢を好きだと認めた場合」
「……おう」
突然直球の言葉が飛び出したので、彰人は面食らいながら相槌を打つ。どうやら話題は続いていたらしい。ちらりと横目で見やると、冬弥はすっと息を吸い、落ち着いた声でとんでもないことを言った。
「ものすごく口説くぞ」
「ものすごく口説く」
あまりのことに反復することしかできなかった彰人を尻目に、冬弥は淡々と続ける。
「練習の合間に所構わずやるぞ」
「そ、そこまで必要か?」
冬弥の場合、比喩でも大げさでもなく本当にそうするだろう。その光景を思い浮かべるだけでこはねに対して同情心さえ湧いてくる。それと、相棒のあんたがどうにかしなさいよと刺してくるだろう杏の冷たい視線まで。想像上の心労に顔をしかめていると、弾みがついたのか冬弥はすらすらと言葉を吐き出した。
「小豆沢は他人の好意をまっすぐ受け止めるタイプだが、だからこそ遠回しなアピールは響かないと踏んでいる。加えてなぜか自己評価が低いところがあるからな、繰り返し言い聞かせてこちらに気持ちを向けさせる」
「こえーよ」
「それと彰人、お前にも協力してもらう」
「オレが?」
急に向けられた矛先に硬直する彰人と対照的に、冬弥の台詞はまるで原稿でも用意していたかのように淀みない。
「なんといっても小豆沢は他校生で本来関わりが少ない。練習で顔は合わせるがチームのための時間だし、俺もそこを疎かにするつもりはない。だが委員会や私用で集まり方がばらけることがあるだろう」
「あーまあ、それなりに」
「たとえば白石だけが委員会で遅くなる時、お前も用事があることにして俺と小豆沢を二人きりにしてくれ」
「……ちょっと引いてきた」
「それから四人で出かけた時もうまく白石を誘導して二人は姿を消してほしい」
「オレは牧羊犬か」
「あと、これは特殊なパターンだが……」
「まだあんの!?」
彰人は目的地まで時間のかかる徒歩を選択したことを後悔しながら、ほとんど悲鳴のように叫んだ。どこかで打ち止めにしないと、授業一コマ分くらいはしゃべりそうな勢いだった。こういうときの冬弥は正直手に負えないし、あの変人を慕っているだけあってやはりエキセントリックな面もあるのだと徐々にわかってきた。遮られたことで区切りがついたのか、冬弥は目もとの力を抜いて軽く息を吐く。
「とまあ、それくらい全力になるがいいんだな?」
いいわけあるか。胸中でぼやき、彰人は眉間を揉むようにおさえた。つまり――
「お前はそこまで考えておきながら、いまはストップかけてるってことか?」
「いま集中するべきはチームの活動だからな」
「そ、そうか……もうちょっと小出しにはできねえの?」
「生憎、彰人のような器用さは持っていないんだ。俺は心を決めたら没頭するタイプだしな」
「は!? 何のこと言って」
反射的に否定しかけたが、彰人は言葉を途中で切った。考えてみれば、話を振ったくせに自分のことを黙秘するのはイーブンではない。なんだか開けなければよかった箱をのぞいてしまった、と思いながら地面へ視線を落とす。その沈黙を冬弥がどう捉えたのかはわからないが、困ったような、もしくはおもねるような含みのある声が夜道に響いた。
「だから、いまは周りが勝手に誤解してくれていれば充分なんだ。後方彼氏面とやらで」
「そうだな、しばらくはそうしてくれ」
とはいえ、先延ばしにしただけでいつかこの計画が実行されるのかと思うと恐ろしすぎる。彰人はどうにかして軌道修正してやらなければ、と考えを巡らせながら地元までの長い帰路を進むことにした。